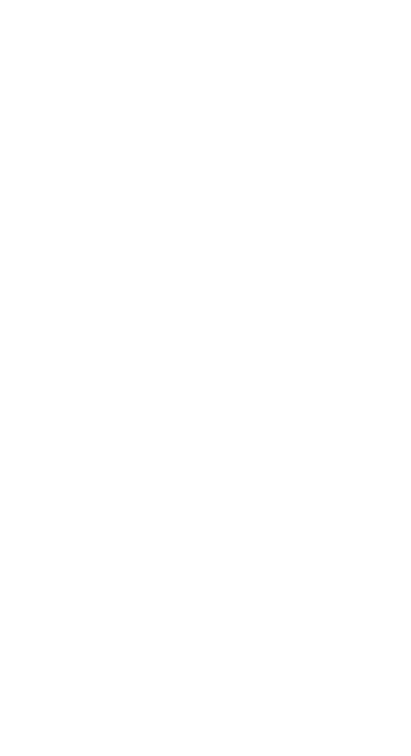JOMON TRAVEL縄文を旅する
なぜ若き縄文アーティストはリアルをめざしたのか〜村上原野くんを偲んで Part.1
2月16日未明、村上原野くんは作陶中にくも膜下出血でこの世を去った。
その手には竹べらが握りしめられていたという。32歳の若さだった。
原野くんは、jomonism企画・制作の縄文アート展「ARTs of JOMON」の常連アーティストだ。父親は、岡山県新見市に拠点を置く縄文アーティストの猪風来さんで、親子でARTs of JOMONに参加いただく機会が多かった。だから、jomonism代表の小林武人から原野くんが亡くなったことを聞いたとき、残された猪風来さんの気持ちを思った。
すぐにお悔やみの手紙を送ると、しばらくしてメールで返事がきた。そこには最期の作品を時間をかけて磨いたこと、それは息子に語りかけ、涙を流しながらの作業だったと書かれていたが、それを春の終わりに焼くことも添えられていた。過去に猪風来さんの野焼きに参加したことのある私たちは、その野焼きに参加することが原野くんへの弔いになると思い、「できることなら参加したい」と、意志表示をしたのだった。
原野くんのこと
原野くんには2つの顔がある。ひとつは、縄文造形家としての顔。もうひとつはC++言語(という私には理解できない高度な技術)を操るコンピュータープラグラマーとしての顔。インターネットで検索すると、「狂える中3女子ボレロ村上」というハンドルネームを持つもうひとりの原野くんに出会えるが、私が知っているのは、縄文造形家としての原野くんと父親の猪風来さんのことだ。
猪風来さんは縄文土器の野焼き技法の第一人者として知られる。1978年に千葉の加曽利貝塚博物館の野焼き同好会で、縄文式の野焼き技法を復活し、それによって一躍ときの人となるが、自分にはまだ「縄文のスピリット」が足りないとし、妻のむらかみよしこさんと2人の息子とともに北海道の原野に移住し、竪穴住居をアトリエに20年間に渡り創作に励む。その猪風来さんが自らの手で産婆し、縄文式英才教育で育てたのが原野くんだった。
この頃の猪風来さんは、春から秋にかけて原生林を切り開いて作った田んぼや畑で野良仕事を行い、冬は竪穴住居のアトリエにこもって作陶するという自然のリズムに沿った創作活動を行っていた。人工的な音はラジオから流れるニュースくらいで、米も足踏み機で脱穀していたというから徹底している。
子どもは親の背中をみて育つというが、原野くんもまた粘土をおもちゃに育った。しかし、デザインを専門とする自由な校風の札幌市立高専(現札幌市立大学)に進んだ後は、ロボコンに出場するなどメカニックの世界を追求するようになる。そして、C++言語を操るコンピュータープログラミングの才能を開くのだ。
幼少時より粘土をおもちゃにしてきたということは、第二の脳と呼ばれる「手」をよく使ってきたということだ。おのずと集中力がついたと思うし、集中してものを作るという点では陶芸もプログラミングも同じ感覚があったのかもしれない。とはいえ、ドのつくほどアナログな縄文暮らしからデジタル世界への飛躍の仕方が尋常ではない。もしかして原野くんは機械的なものに飢えており、その渇望が飛距離を生んだのではないかと考えてみたが、母親のよしこさんは「それは違う」という。
「デジタルかアナログかなどという区別もなく、あの子は独特の世界を持っていました。住んでいた谷間の自然と生活、漫画や小説などの本に培われた創造力、縄文を生きる親の感化などがまぜこぜになっていたようです。数学も好きで、私の兄(数学教師)の盛岡の家に滞在中は、本棚の数学関係の本を寝っ転がって読みふけっていました。プログラミングに興味を持つと、暇があると紙に数式や英字が混ざったメモを書き連ねていたのは、数学の問題を解いているような感じでしたね」
数学が好きということは、意外と論理的だったのだろうか。原野くんは、決して多くは語らない寡黙な人だった。体格は猪風来さんゆずりでがっしりしているが、話すととてもやわらかいし、ちょっとオタクっぽかった。アニメが好きということは、時折話す言葉の端々に感じられた。それが電脳空間では「狂える中3女子ボレロ村上」として、1日多いときで30ツイート打つくらい饒舌になるので、人は見た目では判断できない。
そんな原野くんが父に弟子入りしたのは、「粘土がいちばん手になじむから」という理由からだった。縄文芸術を確立しようと長年孤軍奮闘し、岡山県新見市にその拠点となる美術館を構えた猪風来さんにとって、原野くんが後継者として名乗り出たことは大きな喜びだっただろう。師匠、弟子の関係となり、縄文式の土器作りを基礎からきっちり学び、作家としてとても充実していた時だった。それなのになぜだろう。あまりにも早すぎる死だった。
猪風来美術館へ
野焼き前日に岡山市に住む友人夫婦の家を訪ねた。妻のあきちゃんは、東京でジュエリー作家として活動してきた人で、現在私が行う黒曜石を使ったアクセサリー作りのひな形を作ってくれたのが彼女だった。3.11後、あきちゃんは岡山に移住したが、2014年に猪風来さんが発起人となって新見市の美術館でARTs of JOMONを開催したときにはワークショップの講師も務めた。それをきっかけに猪風来美術館で原野くんに陶芸を教えてもらったことがあるそうで、できるなら野焼きに参加したいという。そこで、翌朝猪風来さんに確認をとると、今回は関係者のみでやることになっているが、特別に許可をもらうことができた。
夕方、猪風来美術館の最寄の方谷駅で、やはり東京からきた映像作家の山岡さんと合流し、点火予定の18時前に猪風来美術館に到着する。美術館前の広場に作られた野炉にはすでに火が灯り、猪風来さんが我々が来るのを待ち構えていた。火除けの麦わら帽子をかぶり、革手袋をはき、綿などでできた耐火性の強い服に身を包んだ参加者の方々が、野炉の周りに集まっている。その中には、昨年隠岐を旅したときにお世話になった米子のたまさんもいる。
すぐに作品が運び出され、炉の真ん中に設置された。遺作となった作品は人の腰ほどもある大きさで、背面は原野くんがこれまで追求してきたスパイラル文様で埋め尽くされていた。しかし1/3を占める前面部には、これまでの作品には見られない表現があった。それは女性の体だった。渦巻く文様と女体はつながっていて、文様から分離して変身する瞬間をとらえたような半文半人の姿をしていた。たまさんが、「縄文のニケだね!」と歓声をあげる。確かに、ギリシア彫刻のサモトラケのニケのように、空に羽ばたこうとしているようにも見えた。
生前の原野くんにインタビューをしたことのある映像作家の山岡さんは、「なぜリアル表現に」と訝しげだ。私もそう思った。これまでの原野くんの作品にこのような写実的な表現を見たことがなかった。原野くんが粘土の上に表してきたのは文様表現で、その意味では文様主体の縄文土器の系譜を継ぐものだった。それがギリシア彫刻のようなリアリズムへと踏み込んだのだから、いったいどんな心境の変化があったのかと不思議に思った。
火のカムイに祈る
校庭に丸くきられた野炉では、遺作を囲むように火が焚かれていた。事前に聞いていた話しでは、これから明朝の日の出まで、土器を遠火であたためる「あぶり焼き」が行われる。猪風来さんが通常行う野焼きは、火の周りに作品を配置し、火のあたる位置をずらしながら全体をあぶっていくが、今回はあまりにも複雑な造形のため、焼成中の爆発を防ぐため野炉の中心に置き、周りから火を徐々に近づけて、日の出とともに火力を強める計画だという。1点に注ぐ人と木材のエネルギー量を考えると、ものすごく贅沢な野焼きだ。失敗なく焼ききろうという猪風来さんの強い思いを感じる。
土器を焼く野焼きには、これまでに何度か参加したことがあるが、作品を割れることなく焼成することにかけては、猪風来さんの野焼きは完璧だった。焼き物は水気に弱い。事前の乾燥はどの焼き物でも行われることだが、それでも粘土に水分が含まれていると焼成途中で水蒸気爆発を起こすし、地面が水分を含んでいてもダメ。だから、猪風来さんは焼く前の野炉をじっくり焼いて、土の中の水分を蒸発させる。さらに本焼きの前に作品全体をじっくりあぶることで、ほぼ割れのない完成度に導くのだ。その分、燃料となる木材を大量に使うため、野炉の脇には日本家屋の太い梁や柱、戸板などの廃材が、分類された状態で山積みに置かれていた。見ていると、みんな慣れた様子で材を抜き、火の周りに置いている。
ほどなくして、炎の前で猪風来さんが話し始めた。
「これが原野の絶作です。ほぼ9割9分完成したところで絶命しました。これは非常に複雑で華麗な文様を刻んでいます。普通の土器は1層で立体が出来上がっていますが、これは見ての通り、約4層が文様をなし、春の沸き立つ女神像が土器、すなわち大地の子宮から沸き立つように作られているようです。これを火の力で焼いて頂いて完結しないと作品として成立しません。
私たち親子の悲願は、この世に縄文(芸術)を復活させること。復活した縄文(芸術)を体得すること。そして新しく創造していくことでした。その創造の分野において、しっかりと新しい縄文の様式美を生み出すことが私たちの悲願だったんです。そして原野はそれを見事にやり遂げた。つまり1万3千年間の縄文の造形美を復活させ、それを新しい21世紀の縄文流儀の様式を確立したのがこの作品だろうと思っています。
原野はこの作品1点を1月中旬からまる1ヶ月間かけて作りました。それを私が約1ヶ月かけて磨き上げました。そして、今日および明日2日間かけて焼き上げることで、この作品に新しい命と魂が宿るはずです。それらをみなさんとともに成し遂げたいと思います。
今日は新月ですので真っ暗闇になります。いくら投光器で照らしても肉眼でこの作品の色を見分けるのは不可能です。太陽の光のもとでみた色調でこの作品がどういう状態にあるかを理解することができるのです。ですから、明日の6時か7時くらいに日が射して、色調から温度がわかれば、それにふさわしいように木を積む。それまではこの火円陣で焼いていきます。
0時以降の1時から5時くらいまでの間に急激にここが冷えるということがあります。雲がかかっていないとすれば、放射冷却現象で急激に冷える時間帯が3時から5時の間に必ず来ます。それによって一気に焼き物を冷やしてしまうことがあるので、冷気に対抗する火力を考える必要があります。
そこをクリアすると太陽が出て全体を温めます。太陽の力は実に偉大です。私たちがいくら火を焚いても太陽の力にはかないません。それほどパワフルな存在です。焚いている火に太陽が降りそそぐと、パワーで野炉が活気づき、野焼きが進行します。今日はこのように静まり返っていますが、明日は風も強まるそうです。明日風が少し吹いてくれると、空気が供給されて野炉の状態がよくなっていくでしょう……」
続いて、野炉に向かい合うようにカムイノミが始まった。カムイノミはアイヌ民族の伝統儀式で、アイヌの人々は何か願いごとがあるときに囲炉裏などの火に向かって祈り、用意した酒や食べ物を火に捧げてきた。この場合、火のカムイは人間の願いを自然界のあらゆるカムイたちに伝える役割を担っている。火のカムイを通じてギフトをもらったカムイたちは「こんないい思いをするなら」と、人間たちの願いを叶える。アイヌの中でもカムイノミに対する考え方はさまざまあるが、カムイノミはアイヌとカムイの近しさを物語る儀式だと思う。
猪風来さんは北海道時代にアイヌから直接カムイノミの仕方を習い、縄文野焼きカムイノミと銘打ち、野焼きの前後に必ずこの儀式を行ってきた。先ほどの話しにもあったように、野焼きは人間の力だけではできない。雨が降ると当然焼くことができないし、風が強過ぎると火が大きくなりすぎてしまう。山の天気は変わりやすい。雲の動き次第で冷気や暖気などが炎に影響を与えるので、野焼きが成功するかどうかは、まさに天の采配とそれを見定める人間の知恵にかかっている。だからこそカムイに贈りものをし、人間に有利に事を運ぶのがカムイノミの狙い。野焼きは人と自然界との共同作業なのだ。
「神様に祈るなんて、そんな非科学的なこと」と、思う人もいるかもしれない。しかし、野焼き歴40年の猪風来さんがカムイノミを必ず行うのは、それが「効く」からだ。ここに来る前に猪風来さんと電話で天気について話したときも「不思議と野焼きをしている間は晴れるんだ。先日も終わったら雨が降ってきてね」と話していた。きちんと祈ると願いは届くものらしい。もちろん、信じるか信じないかはあなた次第だけど。
( Part2へ続く)
村上原野くんの作品が見られる展覧会
「村上原野追悼~渦巻く翅(つばさ)のヴィーナス展」
会期 2020年9月1日(火)~12月26日(土)
休館日 月曜日(冬期12月~1月は月・火曜日)
猪風来美術館(新見市法曽陶芸館)
岡山県新見市法曽609 TEL・FAX (0867)75-2444
詳しくはコチラ
「縄文のスピリットに基づきながら現代に生きる己の感性で
土と炎と大自然に向き合い、縄文の新時代の美を求めてゆく。
やがて皆がそれを感じ、縄文のあたらしい渦が新星のように
生まれてゆく時代――スパイラル・ノヴァの訪れを予感しています。」(村上原野)
今年2月16日未明、作品制作中に手に竹べらを持ったまま32歳の若さで突然逝ってしまった村上原野。
完成直前の絶作となった「渦巻く翅のヴィーナス」をはじめ、10年間に渡って制作された渾身の珠玉作品と
その濃密な創作の過程を一挙展示します。
なぜ若き縄文アーティストはリアルをめざしたのか〜村上原野くんを偲んで Part.2
勾玉でできたアート
陽も暮れて薄暗くなってきた。野炉の周りが落ち着いていたので、校舎に展示された原野くんの作品を見ることにした。猪風来さんに案内されて1階の展示室に入ると、そこは法曽焼作品の部屋だった。法曽焼とは、美術館のある法曽地区で江戸後期に途絶えてしまった幻の陶磁器で、それを現代に復興をしたのも猪風来さんの功績のひとつだ。展示室には、猪風来さんの法曽焼作品のほか、原野くんの手がけたものもあった。
それは8月30日まで開催中の企画展「地より来て地に還るもの」のメインとなる作品だった。猪風来さんの話しによると、絶作の前作にあたるもので「死」をテーマにしているという。赤黒い陶磁器上に鈍く光って流れる渦の起点を指さした猪風来さんは「これはすべて勾玉でできているんだ」と話す。よく見ると、目の前の作品は、勾玉のしっぽを伸ばしたスパイラル文様で埋めつくされていた。
勾玉は縄文時代から古墳時代まで装身具として作られてきたものだ。勾玉の形については、動物の牙を原形とする説や、半割れした玦状耳飾りを再利用したものなどいくつかの説があるが、猪風来さんは「胎芽(胎児の前の段階)の形で、すべての生命の源を表している」として、呪術具だと捉えている。
母親の子宮に着床した小さな受精卵は分裂を繰り返し、魚から両生類、は虫類と、生物の進化の形を辿るが、その初期の形はどの生物も同じ勾玉のような形をしている。猪風来さんは狩猟をしていた頃の人々は、そのことを知っていたと踏んでいる。なぜなら、仕留めた動物を解体し、食べるのが当たり前の暮らしだったからだ(さらに付け加えるなら、流産の多い時代で、自分から流れてしまった胎芽を見る機会があったということも留意しておきたい)。胎芽をいのちの最初の形として認識していた古の人々は、そこに見えない力を感じ、見たままに勾玉をつくり、さらにその形を発展させて土器の上に渦を描いたとする考えが、猪風来さんの縄文芸術の根幹をなしている。
その思想は原野くんにも受け継がれ、より明確にキレのあるスパイラル造形となって、目の前に置かれていた。下から沸き立つようにのぼるいくつもの渦の真ん中にはどれも勾玉があった。じーっと見ていると吸い込まれそうになるサイケデリックな渦は、S字を描きながら上昇し、トップで角を持つ雄鹿の頭に変化していた。その目は勾玉の生命感を断絶するように閉じられていた。リアリズムへの道は、この頃から始まったのだろうか。絶作へ至る道が少しずつ見えてきた。
猪風来さんは野焼きの現場に戻り、私たちはさらに原野くんの作品を見るために2階の展示室へと上がった。階段を登って左の奥にある部屋に入ると、釉薬のかかっていない野で焼かれたザラザラとした土器がずらりと並んでいた。
原野くんは父の猪風来さんに弟子入りしたとき、3年間徹底的に縄文土器の模写を叩き込まれた。猪風来さんが縄文のスピリットを体得するために北海道の原野に分け入ったように、縄文1万年の手仕事を自分のものにするには、まず模倣からというわけだ。壁際には、その頃作ったと思われる縄文土器や土偶が並んでいた。すべていちから粘土を輪積みして作ったものだと思うが、型取りしたレプリカに見えるくらい本物そっくりだった。
次に原野くんが初期に作ったオリジナル土器を見る。それが初期の作品だと知っているのは、この土器を焼いた2014年の春の野焼きに私たちも参加していたからだ。口縁部が流線型になった土器は、jomonism代表で3DCGデザイナーの小林武人がライブペインターの坂巻義徳 a.k.a sense の絵をモデリングし、3Dプリンターで出力したパーツを原野くんに渡して出来たコラボ土器だった。
最初にこの作品をみたとき、土でできた土器なのに、モーターショーに展示されるコンセプトカーのような近未来感を感じたのを覚えている。それは口縁部についた武人のパーツから受ける印象だけではなかった。改めてじっくり観てみると、文様を構成する線に迷いがなく、とてもシャープなのだ。曲線にキレがあるので、スピード感が出る。何のスピードかというと、竹べらを持つ手のスピードだろう。そのスピーディーで流れるような文様が、流線型を描くコンセプトカーのようにキレキレに見えるのだった。
当時、出来上がった作品を見た武人はこんなことを言っていた。
「ずっと模写をしていたからだと思うけど、人のラインをたどるのがすごくうまい。パーツから流れるラインの部分とか、何も言わなくても僕らの形を理解してくれている。すごいと思った。仕上げもとても丁寧だし、土っぽくて自然な雰囲気の猪風来さんの作品とはまた違うんだよね。縄文と現代の感覚が原野くんの中で融合して次世代の土器に昇華されているんだよ」
2年程前になるが、ある縄文ムック本の記事を書くにあたり、原野くんに簡単な電話取材をしたことがある。そのとき彼は初期の創作の源流を北海道で過ごした幼少時代の原風景に求め、あの頃の自分にあった縄文(子ども)の感性を掘り起こすことから始めたと言っていた。そしてこう話していた。
「縄文土器の文様には世代を越えて語り継がれ、地層のように蓄積された世界観があるのだから、その世界観を、現代の自分も学び、取り込んで、次の人間に新たな縄文の種として引き継いでいきたい」
その言葉通り、初期の頃と思われる作品には二つのリングが表裏一体になった双眼や三つ又の三叉文、縄目といった縄文土器に見られる形が散りばめられていた。しかし、順を追うごとに縄文土器っぽさはなりを潜め、曲線への過剰な追求が行われていくのがわかった。部屋の中央に並んだ作品群になると、文様が意志を持った生命体のように大きくうねり、アメーバ状にねじれている。口縁部は閉じられ、もはや器でもなかった。
縄文土器の中には、中部高地に見られる水煙文土器や信濃川沿いの火焔型土器、あるいは3D感が半端ない会津式土器のように過剰な装飾性、立体文様を持つ土器があるが、あれらはあくまでも鍋や瓶といった生活用具だった。縄文土器の面白さはそこにある。なぜ煮炊きに使う鍋に複雑な文様を施したのかということについては、山岡さんの監督した『縄文にハマる人々』を参考にして頂きたいが、縄文土器のデザインは土器の中身(食料としての植物や動物)との関係や、狩猟採集民の世界観(神話観)の共有、血族や出身を表す必要性など、様々な理由があった上で機能していたものだと思う。
しかし、猪風来さんも原野くんもそのような背景から一切切り離された現代に生きている。現代における土器の創造は自己表現なのであって、とくに鍋や器である必要性はない。だから、原野くんは縄文土器の大前提である「器」から離れ、文様のエッセンスを抽出したエネルギー体のようなオブジェとして表したのだろう。
2年前の電話取材で原野くんが話していた内容を紹介したい。
「いま作っている作品は、渦を巻いて動き続けるという縄文(文様)本来の特徴をよりダイナミックに表現したもの。縄文の伝統的な様式には法則性があるが、様式の移り変わりの中でうつろうもの。一万年以上、縄文たらしめた根源にある精神性や哲学が大事で、僕は、自分の作品に”いのち”を込めている。それは土器そのものが”いのち”であるという哲学なんです」
文様(パターン)というものは、制限がなければどこまでも無限に増殖することができる。イスラム教寺院などの例をみても、壁・天井・床などの平面は、アラベスク文様で敷き詰められているはずだ。こと粘土での文様表現になると、平面という制約もなく、文様は縦横無尽に動ける。そのありさまは、自然界のいたるところで増殖するものたち(枝を広げる樹木や樹皮に根を卸す地衣類、生い茂る野草、春になると湧きだすカエルの卵など)の姿に見ることができる。そのような途切れることのないいのちのループは、ときに美しく、ときに恐ろしくなるほどグロテスクだ。そして、生命の持つそのような本質が原野くんの作品群にはよく表れているのだった。
「グロテスク」「装飾」という言葉についての補足
現代では漠然と「気味の悪いもの」をさす「グロテスク」だが、ケルト美術研究の第一人者である鶴岡真弓さんの『「装飾」の美術文明史』(NHK出版)によると、グロテスクという言葉は15世紀の皇帝ネロの「黄金の館(ドゥムス・アウレア)」の洞窟(グロッタ)を連想させる半地下の壁に描かれていた奇妙で不合理で過剰な装飾に起因するという。廃墟となったその建物を再発見したのは、16世紀のイタリア・ルネサンスのラファエロをはじめとする芸術家たちで、植物から人間へ、鳥が人間へ、などという空想に満ちた装飾に刺激を受け、こぞって装飾表現に取り入れたことから、「グロッタ」もの、すなわち「グロテスク」と呼ばれるようになった。鶴岡さんは、ルネサンスの芸術家たちが膨らませたグロテスク装飾は、「ありえない自然」であり「反自然」的だが、同時に細部に徹底した自然観察による自然主義が見られると指摘している。
つまり、「グロテスク」という概念は、もともとは古典美の復興と徹底した自然観察によって創作された装飾の世界から生まれた言葉であり、人を惹き付ける魅力に満ちた世界観があることをここに書いておきたい。ついでに「グロテスク」の語源となった「洞窟」についても言及すると、人が住居で暮らす以前の住まいは洞窟だった。長い期間、暗闇とともに暮らしていた人間には闇という属性があり、それが古い段階の文化では、ストレートに表現されていることが多い。そこにルネサンスの芸術家たちも反応したのではないだろうか。美という価値観は人によってさまざまだが「美しさ」を求める人間の心性は、闇(グロッタ、グロテスク)を知っているから生まれたこと。闇がなければ、美もないのである。
また、縄文土器の文様は「装飾」ではないと思われる方もいるかもしれない。「カザリ」という言葉に対して嫌悪感を抱く人は多いのか、この本もまた、「いつの世にも人は虚飾に欺かれる」というシェイクスピアの『ヴェニスの商人』の引用から始まり、「人は『飾り』とか『装飾』というものを、反射的に『嘘』や『愚かしさ』と結びつけてみることが多い」と指摘している。そして、その考え方が最高点に達したのが、20世紀のモダンデザインにおける、建築家ミース・ファン・デル・ローエが提唱した「レス・イズ・モア(飾りを少なくすればするほど、より機能的な生活ができる)」なのだと。
しかし、飾ることは人間だけが行う行為ではない。「蝶の羽や魚の皮膚や草木の蔓草や花びらなど、自然界全体が『装飾』の営みを持っている。そのなかで人間も『飾る動物』の一員」であり「単に人間の芸術行為に『カザリ』が添えられるというのではなく、文化のコアから現れる人間存在の本質の部分、それが『装飾』」なのだと。その文脈で言えば、縄文土器の文様とは芸術が生まれる以前にあった、この「装飾」行為の源流にあたるものだと思う。そこには、洞窟のごとく真っ暗な竪穴住居で暮らしていた「闇を知っている」人々が求めた、美の形があるはずなのだ。
( Part3へ続く)
村上原野くんの作品が見られる展覧会
「村上原野追悼~渦巻く翅(つばさ)のヴィーナス展」
会期 2020年9月1日(火)~12月26日(土)
休館日 月曜日(冬期12月~1月は月・火曜日)
猪風来美術館(新見市法曽陶芸館)
岡山県新見市法曽609 TEL・FAX (0867)75-2444
詳しくはコチラ
「縄文のスピリットに基づきながら現代に生きる己の感性で
土と炎と大自然に向き合い、縄文の新時代の美を求めてゆく。
やがて皆がそれを感じ、縄文のあたらしい渦が新星のように
生まれてゆく時代――スパイラル・ノヴァの訪れを予感しています。」(村上原野)
今年2月16日未明、作品制作中に手に竹べらを持ったまま32歳の若さで突然逝ってしまった村上原野。
完成直前の絶作となった「渦巻く翅のヴィーナス」をはじめ、10年間に渡って制作された渾身の珠玉作品と
その濃密な創作の過程を一挙展示します。
なぜ若き縄文アーティストはリアルをめざしたのか〜村上原野くんを偲んで Part.3
火と向き合うということ
校庭に戻ると、山岡さんが「ものすごく艶かしくなっていますよ」と野炉の作品を指して言った。最初に据え置かれたときよりも、表面がねっとりと艶を帯び始めていて、まるで汗をかいているように見える。心なしか色も黒ずんだ気がする。炎によって粘土の中で化学変化が起こり始めているのだ。
野焼きに立ち会うと、火の力を思い知らされる。いまこのあぶり焼きの火ですら、1mも近づけないほどの熱量がある。これが明日の本焼きになれば、太陽からの熱量も加わり圧倒的なパワーとなって土器を覆い尽くすのだ。土器は火の力の賜物。腐ってなくなることが宿命の有機物だらけの世界にあって、土を半永久的な形にしたのが火の力だ。火の利用は科学の始まり。鉱物から銅や鉄などを精錬するのも火を扱える技術がなければ始まらない。人間は火を扱うことを通して文明を切り開いてきた。
しかし、いつしか私たちの社会は火を避けるようになった。囲炉裏の火はストーブに代わり、ゴミの野外焼却はダイオキシンが発生するとして禁止された。やがてストーブもエアコンに置き換わり、IHコンロを導入したオール電化の住宅にする人も少なくない。今ではキャンプ場やBBQ場といった限られた場所でしか火を焚くことは許されていない。この野焼きも、消防や自治体への届け出を出した上で行われているはずだ。
たしかに火は危険だし、環境問題にも配慮しなければならない。しかし、暮らしから火を使う機会がなくなることの方が、いろんな意味でリスクがあるような気がしてならない。なぜなら、火の危険性を学ぶ機会ごとなくなるわけだから。
その意味で、土器を焼く野焼きは火の扱い方を学ぶよい機会だと思う。小さな火から大きな火まで体験でき、化学繊維の服は溶けやすいとか、風の強さで火がどう燃えるか、乾燥した木材の火付きの早さなども体感でわかる。猪風来さんはより多くの人が縄文の精神を理解し、縄文造形が定着することを願って、年に2回、春と秋に野焼きを行っているが、それは裏返すと、火の教育をしているようなものだ。土器がうまく焼けるということは、火を上手に扱えるようになった証でもあるのだから。
野炉の周りでは、女性たちが燃えている柱に臆することもなく手をかけて、炎の位置を整えていた。火の扱いがうまく阿吽の呼吸でことが進んでいくのは、見ていてとても安心感があった。
訪れたスランプ
今回の野焼きに集まった人たちは、年齢の幅もさまざまだ。近隣の方もいれば、あきちゃんのように岡山に移住してきた人、旅の途中で偶然ここを見つけ、以来野焼きに参加しているという遠方の方もいた。みんな原野くんの追悼がしたいと集まった方々だった。
広場の端にある工房では、それら参加者が自由に食べられるよう、おにぎりや豚汁、サンドイッチのほか、持ち寄りのお菓子や惣菜が大量に用意されていた。そのテーブルの上に、今年の春の野焼きで焼いたという原野くんの遺作が2つ並んでいた。
小ぶりな作品のほうは、ゆるいカーブを描くS字文様が上へ上へと延びており、透かしの入った面白い形をしていた。しかしもうひとつの作品は、下から続く華麗な文様帯が口縁部で唐突に途切れ、のっぺりとした無文部で終わっていた。
猪風来さんによると、原野くんは口縁部まできて、突然この続きが作れなくなったという。超絶技巧の持ち主で、追求するテーマもしっかり確立していた原野くんが、これを境に冬まで粘土を握れない日々が続いたというのだ。いったい何があったのだろう?
それは、一昨年(2018年)の夏のことだという。ちょうど東京の国立博物館で「縄文―1万年の美の鼓動」展が開催され、縄文ブームが沸き起こっていた頃だ。山岡さんの『縄文にハマる人々』も公開され、映画に登場した猪風来さんや原野くんにも注目が集まっていた時期だと思う。理由はわからないが、子どもの頃から疑いもなく触ってきた粘土への思いがしぼんでしまったのだ。それは粘土を触る自分への信頼が失われてしまったということではないだろうか。
母親のよしこさんにそのときの原野くんの様子を聞くと、粘土造形ができなくなっただけでなく、対人での関わりを避けて、なかば“うつ状態”のようだったという。本人から「そっとしておいてほしい」という要望があり、猪風来さんもよしこさんもストレスを与えないよう見守るしかなかった。しかし、あるとき急に『山に行きたい』と言い出した原野くんは、テントや寝袋をもって、ひとりで隣接する広島県の山に出かけたという。
ある意味、それはネイティブアメリカンにおける成人の通過儀礼、ヴィジョンクエストのような体験だったのだろうか。将来的に猪風来美術館を継いでいくことが決まっていても作家として確立できるかはまた別の話しであり、自分は何がしたいのか、どうあるべきなのかなどと色々考えたいことがあったのだろう。原野くんは山から還ってくると、翌春に決まっていたアメリカでのワークショップの準備に少しづつ取りかかるようになったという。
アメリカ行きの話しは、jomonismのメンバーである陶芸家の大藪龍二郎がその前年度にアメリカに住む友人と企画した続編にあたる機会だった。このとき原野くんはアメリカ側との対応を行い、猪風来さんとともにコロラドの大地で陶器をつくり、野焼きを完遂した。それら一連の経験が糧になったのか、帰国後は吹っ切れたように再び粘土に向き合えるようになったという。そこで生まれたのが法曽焼の雄鹿の作品だ。原野くんは半文半獣の表現に手応えを得たのだろうか。次に半文半人の縄文のニケ(仮題)に挑むのだ。
外に出ると、新月だというのにそれほど星が見えなかった。薄く曇っているのかもしれない。そのせいかそれほど冷込みもきていなかった。野炉では燃焼時間の長い太い木材が時折火の粉をあげて、おだやかに燃えている。野炉の脇で、あきちゃんが静かに涙を流しながら物思いにふけっていた。他の人たちも静かに野炉の作品を見守っていた。深夜0時を過ぎ、女性から男性へ野焼きスタッフの交代が行われたところで私たちは引き上げ、美術館内の使っていない展示室で寝袋を敷いて寝た。
炎を吸って色を変えていく
翌朝、5時を過ぎたところで猪風来さんが私たちを起こしに来た。本焼きが始まるという。火を強めるのは6時か7時くらいからと聞いていたのにだいぶ早い。きっと野炉の土器が待ってくれないのだろう。校庭に出て、寝ぼけ眼で野炉を見ると、青みがかった朝の薄明かりの中で原野くんの縄文のニケ(仮題)はびっくりするぐらい真っ黒になっていた。これは粘土の温度が上がり、煤の吸着が進んだためだ。猪風来さんが丹念に磨いた表面はブロンズ像かと思うくらい黒光りしていた。
火円陣の範囲はだいぶ狭まり、男たちが太い材を井げた状に組んでいく。こうして炎の高さを出していくことで、作品は火で包まれる。その状態を猪風来さんは「火の子宮」と呼ぶ。土は650℃を越えると粘土に戻らなくなるという。土の中に含まれる結晶状の水分が650℃を境に飛ぶためだ。それ過ぎると、粘土の色は黒から赤へと変化するそうだ。猪風来さんの野焼きでは上まですっぽり炎で覆う子宮状態で800℃や900℃を目指す。
7時を過ぎると山際から朝日が差し込んできた。轟々と火力を増した野炉から天に向かってつむじ風が巻き起こり、そこに朝日が当たって何かの合図のように見えた。作品の下半分が赤く染まり出したのが肉眼でも確認できる。問題は、複雑な造形をした背中側で、そこも均等に温度を上げていくために猪風来さんは後ろ側の火の当たり方により注意を払っていた。
8時半を過ぎ、野炉の周りで歓声があがる。とうとう炎の高さが作品を越え、井げたの上に板材が渡されたのだ。作品は炎に包まれとうとう見えなくなった。野焼きの最終局面である火の子宮だ。仕上げに細い枝が周囲に立てかけられると、炎が天を目指して立ちのぼる。一同静かに見守ると、燃焼して弱まる炎の中から、全体が赤茶色に染まった作品が表れた。煙の中から表れた姿は、まさに「ヴィーナスの誕生」といった初々しい雰囲気で、難産で生まれた子どもみたいだった。それまでの緊張感がほどけ、抱き合って涙する参加者もいる。きっと、この瞬間を一番見たかったのは原野くんだっただろう。
2014年に原野くんが最初にオリジナル土器を焼いたとき、感想を聞いたら「わが子のようです」と笑って答えたのを思い出す。その笑顔の後ろに束ねられた髪の毛先はちりちりに焼けていたっけ。雄鹿の作品が「死」をテーマにしていたことから、この作品のテーマは「生」なのではないかと猪風来さんはいう。その「生」の実感は、野焼きという火との丁々発止のやりとりを経験して得られる深い実感なのかもしれない。原野くんは、熱と格闘してものを生み出すことの清々しさを感じていたんだな。
土の手触りや火の熱量が魅了する世界がある。そこは、人間界と自然界がちょうど重なり合う地点。自然界の生き物はDNAというプログラミングされたコードによって、いのちをつなぐように設計されているが、原野くんはきっとそのコードを粘土で表現しようと奮闘していたに違いない。この粘土でどこまで複雑にできるか。重力に逆らってどこまでのばすことができるのか。あらゆるパワーバランスの整合性をとりながら、常に変化し続けるいのちの躍動感を焼き付けようとした。シンプルなモダンデザインに慣れた私たちは、そのうごめく姿にぎょっとする。けれど、文様に埋め尽くされた作品は、こう訴えかけてくる。人間もまた変化し続ける自然の一部なのだということを。
—
なぜ原野くんはリアリズムをめざしたのか。そのことに大きく関係する話としては、やはり女性との出会いがあったということを最後に書いておきたい。その女性の心境を察すると、詳しくはここに書かないが、原野くんは幸せの絶頂にいた。最愛の人との出会いが土器の女神化を後押しした原動力となったのは間違いないようだ。
(FIN)
村上原野くんの作品が見られる展覧会
「村上原野追悼~渦巻く翅(つばさ)のヴィーナス展」
会期 2020年9月1日(火)~12月26日(土)
休館日 月曜日(冬期12月~1月は月・火曜日)
猪風来美術館(新見市法曽陶芸館)
岡山県新見市法曽609 TEL・FAX (0867)75-2444
詳しくはコチラ
「縄文のスピリットに基づきながら現代に生きる己の感性で
土と炎と大自然に向き合い、縄文の新時代の美を求めてゆく。
やがて皆がそれを感じ、縄文のあたらしい渦が新星のように
生まれてゆく時代――スパイラル・ノヴァの訪れを予感しています。」(村上原野)
今年2月16日未明、作品制作中に手に竹べらを持ったまま32歳の若さで突然逝ってしまった村上原野。
完成直前の絶作となった「渦巻く翅のヴィーナス」をはじめ、10年間に渡って制作された渾身の珠玉作品と
その濃密な創作の過程を一挙展示します。
第2回 パワースポットと縄文遺跡 代々木八幡遺跡(東京都)
代々木八幡宮は「都内有数のパワースポット」だという。ネットで検索すると、「仕事運を上げる」や「効く!」として、さまざまな芸能人がお忍びで訪れているとの噂に事欠かない。今年の初詣も参拝客が長蛇の列をつくっている様子がニュースで流れていた。
建立は鎌倉時代。祭神は皇室の祖神や源氏の氏神である軍神の八幡宮(応神天皇)。古くは武将が戦いの前に必ず参拝したとされる代々木八幡宮だが、境内には縄文遺跡が出ており、復元された竪穴住居と遺物の展示が見られる。もしかすると、この場所がパワースポットであることと縄文遺跡は何らか関係があるのではないだろうか。早速、縄文人の審美眼にかなった場所を歩いてみたいと思う。
海の退きはじめた沼地に面した高台の遺跡
縄文遺跡を内包する代々木八幡宮は、幹線道路の山手通りと小田急線の線路が交差する少し北側にある。代々木八幡駅から歩いて行くと、一段上に山手通りが通り、神社はさらにその上の面にある。谷底となる駅のあたりは、渋谷川水系の初台川が暗渠となって遺跡のある台地を回り込むように蛇行して流れている。
ブラタモリよろしく高低差を感じながら山手通りへと続く階段を登り、オベリスクのような首都高山手トンネルの換気塔を左に見ながらしばらく歩くと、右手側にこんもりとした小高い森が見えてくる。これが代々木八幡宮の鎮守の森だ。
交通量の多い山手通りからゆるやかな石段を上っていくと、樹齢を重ねた木々が辺りを包み込み、通りの喧噪が遠のいていく。急に鳥のさえずりが聞こえ、なぜかニワトリの鳴き声も。ここは本当に渋谷区なのかと、異世界に入ってしまったような感覚を覚える。
カーブを描く石段を上がると、参道の脇に竪穴住居が見えてきた。
柵に囲まれているので檻に入れられた動物のようだが、れっきとした竪穴住居だ。きれいな円錐を描く茅葺き屋根に入り口がひとつあり、その上に煙抜きの窓がある。
昭和25年の発掘調査で見つかった同じ場所に復元されたものだ。
遺跡の案内板によると、当時この場所は幡ヶ谷丘陵の南方に突き出した半島の端で、海の退きはじめた沼のようなところに面し、背後にはカシやナラの森が広がっていた。境内には今もアカガシの大木が見られるので、臨場感たっぷりに縄文の森の風景を思い起こさせてくれる。
境内からは縄文時代早期から後期にかけての痕跡が出土している。中でも中期後半(約4500年前)の加曽利E式土器の時代の遺物がもっとも多く、土器のほか石器類が発見されている。
加曽利E式土器の時代
神楽殿の脇にある小さな展示館に発掘された遺物の一部が展示されているというので行ってみることにした。
ガラス張りになった4畳半程の展示スペースには土器を作る妻のもとに、狩りを終えた夫が「ただいま」と帰ってきた様子が再現されている。全身が土気色のうつろな目をした人形に目を奪われてしまいがちだが、注目すべきは、その手前に展示されている土器や石器だ。
最も大きな土器は「埋甕炉(うめがめろ)」で、竪穴住居の炉に埋めて使われていたもの。下半分がないのでこれを灰に埋めると五徳のように使えて便利だったのかもしれない。土器様式としては加曽利E式に見えるが、それ以前の勝坂式土器の名残のような眼鏡状の突起がついている。
勝坂式土器は、縄文時代中期前半を代表する土器で、おもに中部高地から関東西部にかけて見ることが多い。顔がついたり、蛇やカエルといった具象的なモチーフが踊ったり、何かがうごめいているような躍動的な印象を残す文様が特徴的だ。しかし、中期後半からの加曽利E式になると、勝坂式に見られた生命感はなりを潜め、口縁部と胴部が明確に分けられ、縄目の地紋に渦巻きやS字などのモチーフを配置したシンプルな土器が多くなる。そこにどんな価値観の転換があったのかはわからない。文様作りに変わる別のムーブメントが興ったのかもしれないし、あるいは土器作りにかけられる時間がなくなったのかもしれない。
石棒にみる性なるお祭り
土器の手前には直径10cm程の石棒がごろんと横たわっている。
どう見ても男性の股間の間についているアレである。考古学では、祭祀の道具とされる石棒だが、ではこれを使ってどんな祭りをやっていたというのだろう。
男根をモチーフにしたお祭りといえば、思い出されるのが4月に川崎大師近くの金山神社で行われる「かなまら祭」だ。身売りされた遊女たちが花見の時期に地べたに座り男根型の像を持ち寄り宴会をしたのが始まりで、今も桜の時期にいろんなタイプの男根型の神輿が街を練り歩く。女装愛好家や外国人の参加も多く、あの形の神輿を嬉々として担ぐ姿を見たときは、その滑稽さに笑いが止まらなかった。
もし、縄文時代に石棒を使った祭りがあるのなら、あのような大らかなムードに満ちていたのではないかと思う。
この時代に「性」は淫靡なもの、卑猥なものではなく、あっけらかんと笑い飛ばすような愛すべきネタだったのではないだろうか。笑って心をやわらかくすることが、男女和合の素直な道だったかもしれないし、命をつなぐために男女の結びつきをおおいに肯定することが、この時代の生き方だったのではないかとも思えてくる。
縄文時代は子どもの死亡率が高かったといわれる。流産は多かったと想像できるし、出産時に亡くなったり、産後の肥立ちが悪く母親が命を落とすケースもあったに違いない。今よりもはるかに生と死が隣り合わせで、祈り願う毎日であったなら、そこに神社ができる以前の信仰の形を見ることはできないだろうか。
沼地に面した高台は、見晴らしが良く、自然界の神々に祈りを届けるにはぴったりの舞台だ。見通しがきくことは狩りをするのに都合がよい。台地の下からは水が湧く。土地の持っている条件が、生き物が生きやすいようにできているのだ。そのような土地は、足を踏み入れるだけで心地よいはずだ。それが、ここがパワースポットである理由のように思う。
最後にもう一度竪穴住居を見て回り、境内の裏手にあるスロープを下って住宅が立ち並ぶ路地に出た。下り坂の先には小田急線の線路。その向こうに代々木公園の森が見える。アップダウンを描く地形に武蔵野台地の存在感を感じながら、山手通りへ。目の前にそびえるオベリスクを見たら、急に現実に引き戻されて境内で感じたことが白昼夢のように思えてきた。
このタイムスリップ感を味わうだけでも面白い。もしもあなたの家の近くに高台の神社があったら是非訪れてもらいたい。そこは縄文の聖地かもしれないから。
遺跡に行こう!
代々木八幡遺跡
渋谷区代々木5-1-1
小田急線「代々木八幡駅」下車、徒歩5分
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」代々木上原寄り出口より5分
http://yoyogihachimangu.or.jp/index.php
音楽イベントのお知らせ
縄文、アイヌ、沖縄、TOKYOトライバルミュージックの祭典!
縄文トークに草刈が出ます!
MOVEMENTS ONENESS MEETING
創造の伝承 Tradition of Creation
2020年1月26日(日) 旧暦新年開催!
OPEN / CLOSE:15:00 (UNIT 17:00) / 22:30
場所:代官山UNIT & B1FLAT(ex Unice)
東京都渋谷区恵比寿西1-34-17 ZaHOUSE
東急東横線「代官山駅」徒歩2分
詳しくは☟をクリック!
http://onenesscamp.org/
第1回 深すぎる竪穴の謎 大船遺跡(北海道函館市)
南茅部に2mを超える深さの竪穴住居跡があるらしい。
そんなうわさを耳にしたのは、ジョウモニズムというNPOで縄文イベントの企画制作に関わるようになった2010年頃のことだった。
2mというと人の背丈がすっぽり入る大きさだ。当時みる機会のあった竪穴住居の掘り込みは、せいぜい50cmくらいのものだったから、その異様な深さに驚いた。そこに行った人の話を聞くと、「寒さから逃れるためですかね?」と首を傾げていたが、本当のことはわからなかった。
以来、その遺跡−−−−大船遺跡のことが気になっていた。
昆布の町に 出た国宝
出た国宝
本州に向かって伸びる渡島半島。その南東に旧南茅部町は位置する。かつてわたしは、その隣の鹿部という漁村に8歳まで住んでいた。だから南茅部がどういうところか、少しはわかる。
この辺りの海産物はたいてい昆布とホタテ。昆布漁の季節になると、漁師の子どもたちは早起きをして、丸石を敷き詰めた干し場に親の採ってきた真昆布を広げてから学校に来ていた。てっきり南茅部も同じような町だと思っていたら、北海道にいる父から「南茅部は昔から天皇に献上する昆布を輩出している土地だ」と聞いて驚いた。調べてみると、献上昆布は「白口浜真昆布」といって、高級だしの茅乃舎にも選ばれる昆布の最高級ブランドになっていた。
沿岸漁業の研究者だった父によると、この辺りの海は春先に北から流れ込む寒流、秋に日本海を北上し津軽海峡に流れ込む暖流、さらに海峡に働く潮汐流の影響で、潮目が変わりやすい。拡散された水が昆布によい環境をつくるのだ。
「高台から海をみると、潮の目がはっきりわかる」と父はいった。寒流の勢いが増す春先にマダラやニシンが南下し、次に暖かい海域を好むマグロが寒流を避けるように北上してくる。海が安定している夏はイカ。南茅部は複雑な潮目を読んできた漁師の生きる町なのだ。

しかし、近年南茅部では2つの大きな出来事が起こっていたようだ。ひとつは平成の大合併による2004年の函館市への編入。ふたつ目はその3年後に著保内野遺跡出土の中空土偶が国宝に指定されたこと。なんと北海道初の国宝である。
それを知って俄然わたしは盛り上がった。「あの南茅部から国宝が出た。しかも国宝を展示する施設はかつて叔母が住んでいた臼尻地区にあるじゃないか!」
そういう自分にしかわからない発見が続くと、人間は単純なもので「これは何かのメッセージなのではないか」と思ってしまう。そして「呼ばれているのだ」と解釈し、もう30年も訪れていない故郷のことを思ったりした。しかし、残念ながらその機会はなかなか訪れなかった。年に一度、正月に帰省する実家は小樽にあり、南茅部はもちろん、高校生まで過ごした函館に立ち寄るのは、運転免許を持っていないわたしにはハードルの高いことだった。
津軽海峡を行き来した人々
それから3年ほどの月日が過ぎ、わたしは「縄文と再生」がテーマの野外フェスで出会った東京三鷹出身の縄文顔のカメラマンと意気投合した。写真はほぼ独学という彼の写真は、色調もコントラストもパキッと鮮やかで、フェスの夜の怪しげな雰囲気をよく捉えていた。フィルムカメラを経験していない根っからのデジタル世代。それが、「矢じり」ことヨッシー。
彼は小学校低学年から不登校を決め込んだ筋金入りの問題児だが、車が好きで、モータースポーツをしていた頃に峠道で全損を2回経験して以来、安全運転をモットーにしている。丁寧に運転することから、車のムービー撮影のドライバーもこなす。そんな運転慣れしたカメラマンのパートナーを得て、青森の三内丸山遺跡でジョウモニズムが企画していた野外フェスFeel the Rootsに参加した帰りに、青森港から函館行きのフェリーに乗り込んだのだ。9月の上旬のことだった。

函館に入ってから、2日間雨が続いていた。このあたりは北海道の中では暖かい地域だが、空気は冷たく秋はすでに始まっていた。清流の流れる川汲峠を抜けていくと、海岸沿いの国道の一本山手側に真新しいバイパスができていた。森を切り開いてできた、高速道路のようにまっすぐな道路を北上し、北海道唯一の国宝である中空土偶を展示する函館市縄文文化交流センターへ向かう。
照明を絞った天井の高い展示室の壁一面にこの地域で出た大小さまざまな土器がオブジェのように展示されていた。打楽器のコンガの形に似た細長い土器は、青森の三内丸山遺跡などでみる円筒土器とほぼ同じつくりをしている。
円筒土器は2つの種類がある。先に出現する円筒下層式は口縁部と胴体にそれぞれ違うパターンの縄目をつけたもの。印象としては実に地味だが、どの土器も縄目の入れ方は一定ではなく、さまざまに転がして試した様子がうかがえる。その次の円筒上層式になると、口縁部が波打ち、ヘリンボーンのような美しい縄目の上に細い粘土紐を貼り付けた装飾性豊かなデザインに変わっていく。その間、およそ1000年。文様の技がゆっくり時間をかけて成熟していったのがわかる。


北海道南部と北東北は、縄文時代を通じて同じ型式の土器が出土するため津軽海峡文化圏とも呼ばれている。これらの地域ではすでに縄文時代から人の往来があり、それはのちのアイヌや和人にも引き継がれ、さまざまな交易品が津軽海峡を行き来した。それゆえに津軽海峡は「しょっぱい川」と呼ばれる。
しかし、津軽海峡は決して穏やかな川ではない。
行きのフェリーでも陸奥湾を過ぎると下からつきあげてくる波のうねりが感じられた。いったい波の高い海峡をどうやって渡ったのだろう?
考えられるのは丸木舟だが、手漕ぎの小さな舟で複雑な潮流の流れる津軽海峡を渡れるものだろうか。漕ぐ技術はもちろん、寒流や暖流、潮汐流といった潮を読む知識、そして度胸……あらゆる能力が長けていないと渡れないように思う。
でも、残された遺物がその事実を語る以上、そういうことなのだろう……。
後晩期になると、器形は小さいながらも手の込んだ職人技のような土器が現れる。やかんや急須の原型とでもいうべき注口土器は、縄目と無文部のコントラストが美しい磨消(すりけし)縄文が施され、よく磨かれて艶を帯びており、赤漆で着色された跡を残すものもあった。
国宝土偶に刻まれた指紋
そして照明を落とした特別室に、空を見上げる姿勢の土偶がいた。
中が空洞なことから中空土偶と呼ばれるこの土偶は、およそ3500年前の墓に副葬されたもので、高さが41.5cmもあり、日本最大級の大きさを誇る。南茅部ではこのような土偶の出土例がほとんどないため、よそから運ばれた可能性がある。薄いところで3mmという厚さでありながら、両腕と頭部の突起が欠けているだけで、それ以外は当時の形を保っていることが奇跡のようでもある。


目をひくのはボディに刻まれた文様で、肩から胸、腰から足首にかけて、レリーフ状の細い線が円や菱を描いている。
ゆるやかさと鋭さの織りなす曲線の印象は、アイヌ文様の世界にも通じる。
やや上向きの顔は眉と鼻がつながった凛々しい表情で、八戸の風張遺跡から出ている合掌土偶の顔に似ている。胸からへそにかけて妊娠時にみられる正中線らしきものが降りているが、ヒゲや腹毛のような表現があり、男か女かの判別が難しい。
解説によると、中空土偶のつくられた縄文時代後期は、それまでの土偶にみられた女性(母性)的表現がなくなり、土偶は性別を超えた表現をするものも出てくるそうだ。
しかし、これは本当に土偶なのだろうか。わたしがこれまで中部高地や関東でみた土偶の多くは、敢えて人には近づけないという暗黙の了解があるように抽象化していた。それなのに、なぜここまで人間らしいプロポーションをしているのか謎だった。中空土偶は人間に近いリアルな造形という点で、縄文時代のどの土偶よりも異質な存在感を放つのだ。
施設の許可をとり、展示ケース越しに土偶の頭部を撮影していた矢じりが、「ねえ、これ指紋じゃない?」と、カメラの画面を指していう。拡大すると、頭部の穴からみえる顔の内側に確かに指紋のような跡がみえる。粘土に押しつけられた指紋は風化もせずにやけに生々しく残っていた。
学芸員さんに指紋について尋ねると、それは初見だと驚かれていたので、わたしたちは世紀の大発見でもしたように興奮した。
この指紋の持ち主こそ、土でできた人形に文様を刻んだ張本人なのだ。現代では土偶だけが一人歩きして、国宝5体がそろうと「神ファイブ」などと呼ばれたりする。でも、土偶は神ではなく人間がつくったものだ。それが現代においても人の心を動かし、国宝という価値をまとい、この場所に人を呼ぶ起爆剤になっていることが素晴らしいことなのだ。
リスペクトすべきは、顔も名前も知らない手先の器用な先人なのだから。

なぜ深い竪穴を掘ったのか?
博物館を出るとき、学芸員さんに大船遺跡へ向かうと伝えると、「あの辺には野生化した馬がいるから気をつけて」と言われた。なんでも放牧していた馬が逃げて自然繁殖しているという。馬は有害鳥獣ではないから駆除の対象にはならないらしい。これが都市部であれば社会問題に発展してしまいそうなものだが、さすが全国の森林面積の約1/4を保有する北海道には馬が生きのびる余白がある。
車に乗り込み、海沿いの国道に入る。大船川の河口を渡り、遺跡の看板を山側に曲がると、急勾配の坂が続いていた。南茅部の縄文遺跡は海岸線から1段、2段上がった崖の上に集中している。これは、当時の海水面が縄文海進の影響で数メートル高かったためだ。
坂を登りきると、まばらに並んだ墓の向こうに大船遺跡がみえてきた。残念ながら、野生化した馬はいなかったが、海に向かって開かれた芝地に、骨組みだけのスケルトン状の構造物が2棟、茅葺きの住居1棟と、竪穴2つが復元されていた。
噂に聞いた2mの竪穴は、地面を掘り込んだ穴のみの遺構として地面にぽっかりと口を開けていた。実際には2.4mもの深さがあり、直径8〜11mの楕円形で、深いだけではなく、とても大きい。柱の穴も太く、当時はがっしりとした大きな建物が立っていたことがうかがえる。
床には石組みの炉が復元され、その中に土器が埋められている。炉の周りだけなら本州の縄文遺跡と同じなのに、ここまで深い竪穴はみたことがなかった。ほぼ地下室に暮らしていたといってもいいくらいの深さだ。他に復元されている竪穴もやはり深めで1mくらいある。屋根がついて火を炊いたら冬でもずいぶんあたたかかったのでは……。やはり暖をとるためなのだろうか。

ここに縄文集落が営まれたのは、およそ5400年前から4100年前の縄文時代中期。博物館でみた中空土偶より1000年以上古い時代の遺跡だ。限られた敷地に長く人が住んだため、発掘時は折り重なるように120軒もの建物の跡が出たという。一時期に換算すると、多いときで10軒程度が並ぶ高台の集落だ。
崖のきわまでいくと、白く霞んだ空と海がみえた。晴れていれば海がきれいにみえることだろう。ここに暮らしていた人々は日がな一日海をみつめ、漁に明け暮れていたに違いない。遺跡の北側にある盛土からは、大量の土器や石器のほか、マグロやサケなどの魚類、クジラやイルカ、さらにはオットセイのような海獣の骨などもみつかっているそうだ。

小さな展示室の脇に無造作に積み上がった大量の石皿があった。
石皿は今で言えばすり鉢や作業台のようなもので、クリやドングリなどを主食としていた人々が、硬い殻を石でかち割ったりすりつぶしたり、あるいは道具の加工のために使う台として、全国の縄文遺跡から出土する。

驚くべきことに、大船遺跡ではこの石皿(台石)が4000点以上もの膨大な数で出土している。遺跡が存続した約1300年間に換算すると、1年に3個新しくする計算だ。石材はこの辺りの基盤岩である大船川の河口に落ちている安山岩なので、大船遺跡に暮らした人々は石を贅沢に使ったようだ。
赤い土の秘密
しかし、なぜ2m以上もの竪穴を掘ったのかという理由についてはどこにも書かれていなかった。そこで、隣にいる相方に振ってみた。
縄「なぜここまで掘ったのか謎だよね」
矢じり「縄文時代の人は筋肉隆々だったんじゃない?」
縄「でも、ひとりじゃできないよねぇ。たとえばソーラン節のような作業歌があったとか。男も女もうたいながら楽しく掘っていたら、こんなに深く掘ってしまったとか」
矢じり「ふーん。楽しかったかもしれないけど、確信がないのにこれだけ掘るかな? 僕なら途中で嫌になる。これが正しいと知っていたから掘ったんだよ」
最後は自分のことのように返されてしまった。
後日遺跡の発掘調査をしている学芸員の福田さんにお話を聞いてみると、「明確なことは言えませんが」と前置きした上で、竪穴の床面はローム層まで掘り込んでいるのだと教えてくれた。
ロームとは黄砂、火山灰などを含む埃やチリが風化し、長い時間をかけて堆積した地層で、有名なものには関東ローム層がある。栄養に乏しいためカビやコケなどが生えづらい。つまり、住居の床面にするには適した土壌なのだ。しかし、たびたび噴火する駒ケ岳の影響で段丘上には火山灰が厚く堆積しているため、深く掘らないとローム層は出てこない。つまり、必要な条件を満たす床面が出てくるまで掘った可能性がある。
竪穴住居に住むということは土間の暮らしなのだ。どのような土であれば固く締まり、ものが腐りにくいのかなどの土を選ぶための知恵の蓄積があって然るべきだろう。
福田さんによると、ロームは最初黄土色をしているが、酸化が進むと赤みがかった色になる性質があるという。赤は縄文人にとって特別な色だ。先ほどの縄文文化交流センターには赤く塗られた土器の展示があったし、北海道では墓から赤いベンガラ(酸化鉄)を撒いた跡も出ているのだ。
赤は「情熱」を表す色。ふだん色気のない私でも、ここぞというときには赤を着たくなるときがある。赤は華やかだし、着ることで気持ちが前向きになる「勇気をくれる色」だと思っている。
では自然の中で赤はどんな色だろうか。
身近なところではわたしたちの体内を流れる血の色であり、生まれたての赤ちゃんの色。植物でいえば常緑樹の新芽は赤色をしているし、冬が到来する前に山が一気にみせる紅葉の色でもある。赤は自然界において季節の変わり目にポッと現れるメッセージのような色なのだ。そして子どもを生み育てる女性にも毎月その印は現れる。
赤を生命に関する神秘を秘めた色であり、パワーを秘めた色として祭祀などで多用されたのではないだろうか。
大船遺跡に暮らした人々が、竪穴住居の床面に赤土を選んだかどうかは「わからない」が、土をどう見分けるかという視点がなければ、地面に穴を掘る竪穴住居の暮らしは成り立たないように思う。もし縄文人に脈々と語り継がれた土選びの知恵があったなら、「赤土を選べ」という教えがあってもおかしくないのではないか。

生きのびるためのまじない
福田さんからは、大船遺跡にある別の竪穴住居の床面から胎盤(胞衣)とみられる成分が検出されたことも聞いた。胎児と母体をつなぐ胎盤を小さな壺に入れて人に踏まれるところに埋める胞衣納めは、たくさんの人が踏むことで丈夫に育つとして、自宅出産が行われていた昭和の始め頃まで続いていたまじないだ。
そもそも子どもは身体が未熟で感染症にかかりやすく、いつ死んでしまうかわからない。国の人口動態統計をみると、新生児が1年以内に亡くなる割合は昭和の初め頃までで10人に1人。医療が発達する以前の出産は命がけの行為であり、命を落とすのは母親であることも少なくなかっただろう。
昔の人は病気や災いを魔物のしわざとしたから、魔除けのまじないがさまざまに発達したのだ。大船遺跡の人々も生きのびるためにさまざまなまじないを行っていたに違いない。

縄文時代の古人骨の研究によると、北海道や東北のような寒冷地ほど多産多死の傾向が強くなるそうだ。先ほどの縄文交流センターでは、粘土に子どもの足形を押しつけて、ひもを通して吊るせるようにした土版をみた。センターの南側斜面に広がる垣ノ島遺跡から出土したものだ。子どもの成長を祝った記念なのか、それとも亡くなった子どもの形見なのかわからないが、これもまた、まじないを感じるものだった。
目の前に広がる海は、大漁と不漁、シケと凪、ラッキーとアンラッキーが隣り合わせで、食料をくれるが簡単に人の命を奪う大きな力を持っている。人間は自然界におけるちっぽけな存在なのだ。
だが、大船遺跡の人々はやられてばかりではなかったと思う。なぜなら、人々は津軽海峡を渡ったし、条件のよい土をめざして掘ることもできたのだから。大船遺跡の人々は潮流や地質を見分ける目を持っていた。それは、人々が自然を五感で観察し、そこに法則性を見出していたからではないだろうか。
私は、はるか昔にここで暮らした人々が自然と対話していたことを想像する。胞衣を土に埋めるように、みえない力に働きかけようと、さまざまな方法で「ツキを呼び込む」努力をしたように思う。
リアルな世界と目にはみえない世界。その両方から考えないと、縄文文化の本質はみえてこないのだと思う。赤い色にこだわるのも深すぎる竪穴も、人々が自然界の神々から「いかに愛を引き出すか」を真剣に考えた痕跡かもしれないのだから。

遺跡に行こう!
先に博物館で出土したものを見てから遺跡に行くと、イメージがわきやすい。博物館は休館日を確認するのを忘れずに。
函館市縄文文化交流センターの海側にある垣ノ島遺跡は2021年に向けて整備中だ。
【大船遺跡】
北海道函館市大船町575−1
https://jomon-japan.jp/jomon-sites/ofune/
【函館市縄文文化交流センター】
函館市臼尻町551-1
電話番号:0138-25-2030
http://www.hjcc.jp/