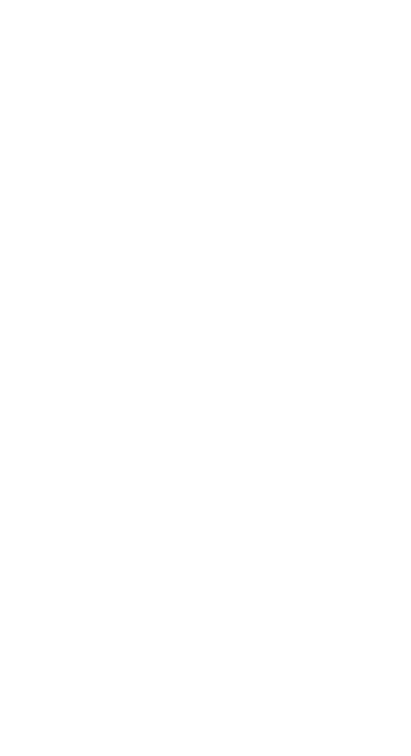JOMON TRAVEL縄文を旅する
北海道第1回 深すぎる竪穴の謎 大船遺跡(北海道函館市)
南茅部に2mを超える深さの竪穴住居跡があるらしい。
そんなうわさを耳にしたのは、ジョウモニズムというNPOで縄文イベントの企画制作に関わるようになった2010年頃のことだった。
2mというと人の背丈がすっぽり入る大きさだ。当時みる機会のあった竪穴住居の掘り込みは、せいぜい50cmくらいのものだったから、その異様な深さに驚いた。そこに行った人の話を聞くと、「寒さから逃れるためですかね?」と首を傾げていたが、本当のことはわからなかった。
以来、その遺跡−−−−大船遺跡のことが気になっていた。
昆布の町に 出た国宝
出た国宝
本州に向かって伸びる渡島半島。その南東に旧南茅部町は位置する。かつてわたしは、その隣の鹿部という漁村に8歳まで住んでいた。だから南茅部がどういうところか、少しはわかる。
この辺りの海産物はたいてい昆布とホタテ。昆布漁の季節になると、漁師の子どもたちは早起きをして、丸石を敷き詰めた干し場に親の採ってきた真昆布を広げてから学校に来ていた。てっきり南茅部も同じような町だと思っていたら、北海道にいる父から「南茅部は昔から天皇に献上する昆布を輩出している土地だ」と聞いて驚いた。調べてみると、献上昆布は「白口浜真昆布」といって、高級だしの茅乃舎にも選ばれる昆布の最高級ブランドになっていた。
沿岸漁業の研究者だった父によると、この辺りの海は春先に北から流れ込む寒流、秋に日本海を北上し津軽海峡に流れ込む暖流、さらに海峡に働く潮汐流の影響で、潮目が変わりやすい。拡散された水が昆布によい環境をつくるのだ。
「高台から海をみると、潮の目がはっきりわかる」と父はいった。寒流の勢いが増す春先にマダラやニシンが南下し、次に暖かい海域を好むマグロが寒流を避けるように北上してくる。海が安定している夏はイカ。南茅部は複雑な潮目を読んできた漁師の生きる町なのだ。

しかし、近年南茅部では2つの大きな出来事が起こっていたようだ。ひとつは平成の大合併による2004年の函館市への編入。ふたつ目はその3年後に著保内野遺跡出土の中空土偶が国宝に指定されたこと。なんと北海道初の国宝である。
それを知って俄然わたしは盛り上がった。「あの南茅部から国宝が出た。しかも国宝を展示する施設はかつて叔母が住んでいた臼尻地区にあるじゃないか!」
そういう自分にしかわからない発見が続くと、人間は単純なもので「これは何かのメッセージなのではないか」と思ってしまう。そして「呼ばれているのだ」と解釈し、もう30年も訪れていない故郷のことを思ったりした。しかし、残念ながらその機会はなかなか訪れなかった。年に一度、正月に帰省する実家は小樽にあり、南茅部はもちろん、高校生まで過ごした函館に立ち寄るのは、運転免許を持っていないわたしにはハードルの高いことだった。
津軽海峡を行き来した人々
それから3年ほどの月日が過ぎ、わたしは「縄文と再生」がテーマの野外フェスで出会った東京三鷹出身の縄文顔のカメラマンと意気投合した。写真はほぼ独学という彼の写真は、色調もコントラストもパキッと鮮やかで、フェスの夜の怪しげな雰囲気をよく捉えていた。フィルムカメラを経験していない根っからのデジタル世代。それが、「矢じり」ことヨッシー。
彼は小学校低学年から不登校を決め込んだ筋金入りの問題児だが、車が好きで、モータースポーツをしていた頃に峠道で全損を2回経験して以来、安全運転をモットーにしている。丁寧に運転することから、車のムービー撮影のドライバーもこなす。そんな運転慣れしたカメラマンのパートナーを得て、青森の三内丸山遺跡でジョウモニズムが企画していた野外フェスFeel the Rootsに参加した帰りに、青森港から函館行きのフェリーに乗り込んだのだ。9月の上旬のことだった。

函館に入ってから、2日間雨が続いていた。このあたりは北海道の中では暖かい地域だが、空気は冷たく秋はすでに始まっていた。清流の流れる川汲峠を抜けていくと、海岸沿いの国道の一本山手側に真新しいバイパスができていた。森を切り開いてできた、高速道路のようにまっすぐな道路を北上し、北海道唯一の国宝である中空土偶を展示する函館市縄文文化交流センターへ向かう。
照明を絞った天井の高い展示室の壁一面にこの地域で出た大小さまざまな土器がオブジェのように展示されていた。打楽器のコンガの形に似た細長い土器は、青森の三内丸山遺跡などでみる円筒土器とほぼ同じつくりをしている。
円筒土器は2つの種類がある。先に出現する円筒下層式は口縁部と胴体にそれぞれ違うパターンの縄目をつけたもの。印象としては実に地味だが、どの土器も縄目の入れ方は一定ではなく、さまざまに転がして試した様子がうかがえる。その次の円筒上層式になると、口縁部が波打ち、ヘリンボーンのような美しい縄目の上に細い粘土紐を貼り付けた装飾性豊かなデザインに変わっていく。その間、およそ1000年。文様の技がゆっくり時間をかけて成熟していったのがわかる。


北海道南部と北東北は、縄文時代を通じて同じ型式の土器が出土するため津軽海峡文化圏とも呼ばれている。これらの地域ではすでに縄文時代から人の往来があり、それはのちのアイヌや和人にも引き継がれ、さまざまな交易品が津軽海峡を行き来した。それゆえに津軽海峡は「しょっぱい川」と呼ばれる。
しかし、津軽海峡は決して穏やかな川ではない。
行きのフェリーでも陸奥湾を過ぎると下からつきあげてくる波のうねりが感じられた。いったい波の高い海峡をどうやって渡ったのだろう?
考えられるのは丸木舟だが、手漕ぎの小さな舟で複雑な潮流の流れる津軽海峡を渡れるものだろうか。漕ぐ技術はもちろん、寒流や暖流、潮汐流といった潮を読む知識、そして度胸……あらゆる能力が長けていないと渡れないように思う。
でも、残された遺物がその事実を語る以上、そういうことなのだろう……。
後晩期になると、器形は小さいながらも手の込んだ職人技のような土器が現れる。やかんや急須の原型とでもいうべき注口土器は、縄目と無文部のコントラストが美しい磨消(すりけし)縄文が施され、よく磨かれて艶を帯びており、赤漆で着色された跡を残すものもあった。
国宝土偶に刻まれた指紋
そして照明を落とした特別室に、空を見上げる姿勢の土偶がいた。
中が空洞なことから中空土偶と呼ばれるこの土偶は、およそ3500年前の墓に副葬されたもので、高さが41.5cmもあり、日本最大級の大きさを誇る。南茅部ではこのような土偶の出土例がほとんどないため、よそから運ばれた可能性がある。薄いところで3mmという厚さでありながら、両腕と頭部の突起が欠けているだけで、それ以外は当時の形を保っていることが奇跡のようでもある。


目をひくのはボディに刻まれた文様で、肩から胸、腰から足首にかけて、レリーフ状の細い線が円や菱を描いている。
ゆるやかさと鋭さの織りなす曲線の印象は、アイヌ文様の世界にも通じる。
やや上向きの顔は眉と鼻がつながった凛々しい表情で、八戸の風張遺跡から出ている合掌土偶の顔に似ている。胸からへそにかけて妊娠時にみられる正中線らしきものが降りているが、ヒゲや腹毛のような表現があり、男か女かの判別が難しい。
解説によると、中空土偶のつくられた縄文時代後期は、それまでの土偶にみられた女性(母性)的表現がなくなり、土偶は性別を超えた表現をするものも出てくるそうだ。
しかし、これは本当に土偶なのだろうか。わたしがこれまで中部高地や関東でみた土偶の多くは、敢えて人には近づけないという暗黙の了解があるように抽象化していた。それなのに、なぜここまで人間らしいプロポーションをしているのか謎だった。中空土偶は人間に近いリアルな造形という点で、縄文時代のどの土偶よりも異質な存在感を放つのだ。
施設の許可をとり、展示ケース越しに土偶の頭部を撮影していた矢じりが、「ねえ、これ指紋じゃない?」と、カメラの画面を指していう。拡大すると、頭部の穴からみえる顔の内側に確かに指紋のような跡がみえる。粘土に押しつけられた指紋は風化もせずにやけに生々しく残っていた。
学芸員さんに指紋について尋ねると、それは初見だと驚かれていたので、わたしたちは世紀の大発見でもしたように興奮した。
この指紋の持ち主こそ、土でできた人形に文様を刻んだ張本人なのだ。現代では土偶だけが一人歩きして、国宝5体がそろうと「神ファイブ」などと呼ばれたりする。でも、土偶は神ではなく人間がつくったものだ。それが現代においても人の心を動かし、国宝という価値をまとい、この場所に人を呼ぶ起爆剤になっていることが素晴らしいことなのだ。
リスペクトすべきは、顔も名前も知らない手先の器用な先人なのだから。

なぜ深い竪穴を掘ったのか?
博物館を出るとき、学芸員さんに大船遺跡へ向かうと伝えると、「あの辺には野生化した馬がいるから気をつけて」と言われた。なんでも放牧していた馬が逃げて自然繁殖しているという。馬は有害鳥獣ではないから駆除の対象にはならないらしい。これが都市部であれば社会問題に発展してしまいそうなものだが、さすが全国の森林面積の約1/4を保有する北海道には馬が生きのびる余白がある。
車に乗り込み、海沿いの国道に入る。大船川の河口を渡り、遺跡の看板を山側に曲がると、急勾配の坂が続いていた。南茅部の縄文遺跡は海岸線から1段、2段上がった崖の上に集中している。これは、当時の海水面が縄文海進の影響で数メートル高かったためだ。
坂を登りきると、まばらに並んだ墓の向こうに大船遺跡がみえてきた。残念ながら、野生化した馬はいなかったが、海に向かって開かれた芝地に、骨組みだけのスケルトン状の構造物が2棟、茅葺きの住居1棟と、竪穴2つが復元されていた。
噂に聞いた2mの竪穴は、地面を掘り込んだ穴のみの遺構として地面にぽっかりと口を開けていた。実際には2.4mもの深さがあり、直径8〜11mの楕円形で、深いだけではなく、とても大きい。柱の穴も太く、当時はがっしりとした大きな建物が立っていたことがうかがえる。
床には石組みの炉が復元され、その中に土器が埋められている。炉の周りだけなら本州の縄文遺跡と同じなのに、ここまで深い竪穴はみたことがなかった。ほぼ地下室に暮らしていたといってもいいくらいの深さだ。他に復元されている竪穴もやはり深めで1mくらいある。屋根がついて火を炊いたら冬でもずいぶんあたたかかったのでは……。やはり暖をとるためなのだろうか。

ここに縄文集落が営まれたのは、およそ5400年前から4100年前の縄文時代中期。博物館でみた中空土偶より1000年以上古い時代の遺跡だ。限られた敷地に長く人が住んだため、発掘時は折り重なるように120軒もの建物の跡が出たという。一時期に換算すると、多いときで10軒程度が並ぶ高台の集落だ。
崖のきわまでいくと、白く霞んだ空と海がみえた。晴れていれば海がきれいにみえることだろう。ここに暮らしていた人々は日がな一日海をみつめ、漁に明け暮れていたに違いない。遺跡の北側にある盛土からは、大量の土器や石器のほか、マグロやサケなどの魚類、クジラやイルカ、さらにはオットセイのような海獣の骨などもみつかっているそうだ。

小さな展示室の脇に無造作に積み上がった大量の石皿があった。
石皿は今で言えばすり鉢や作業台のようなもので、クリやドングリなどを主食としていた人々が、硬い殻を石でかち割ったりすりつぶしたり、あるいは道具の加工のために使う台として、全国の縄文遺跡から出土する。

驚くべきことに、大船遺跡ではこの石皿(台石)が4000点以上もの膨大な数で出土している。遺跡が存続した約1300年間に換算すると、1年に3個新しくする計算だ。石材はこの辺りの基盤岩である大船川の河口に落ちている安山岩なので、大船遺跡に暮らした人々は石を贅沢に使ったようだ。
赤い土の秘密
しかし、なぜ2m以上もの竪穴を掘ったのかという理由についてはどこにも書かれていなかった。そこで、隣にいる相方に振ってみた。
縄「なぜここまで掘ったのか謎だよね」
矢じり「縄文時代の人は筋肉隆々だったんじゃない?」
縄「でも、ひとりじゃできないよねぇ。たとえばソーラン節のような作業歌があったとか。男も女もうたいながら楽しく掘っていたら、こんなに深く掘ってしまったとか」
矢じり「ふーん。楽しかったかもしれないけど、確信がないのにこれだけ掘るかな? 僕なら途中で嫌になる。これが正しいと知っていたから掘ったんだよ」
最後は自分のことのように返されてしまった。
後日遺跡の発掘調査をしている学芸員の福田さんにお話を聞いてみると、「明確なことは言えませんが」と前置きした上で、竪穴の床面はローム層まで掘り込んでいるのだと教えてくれた。
ロームとは黄砂、火山灰などを含む埃やチリが風化し、長い時間をかけて堆積した地層で、有名なものには関東ローム層がある。栄養に乏しいためカビやコケなどが生えづらい。つまり、住居の床面にするには適した土壌なのだ。しかし、たびたび噴火する駒ケ岳の影響で段丘上には火山灰が厚く堆積しているため、深く掘らないとローム層は出てこない。つまり、必要な条件を満たす床面が出てくるまで掘った可能性がある。
竪穴住居に住むということは土間の暮らしなのだ。どのような土であれば固く締まり、ものが腐りにくいのかなどの土を選ぶための知恵の蓄積があって然るべきだろう。
福田さんによると、ロームは最初黄土色をしているが、酸化が進むと赤みがかった色になる性質があるという。赤は縄文人にとって特別な色だ。先ほどの縄文文化交流センターには赤く塗られた土器の展示があったし、北海道では墓から赤いベンガラ(酸化鉄)を撒いた跡も出ているのだ。
赤は「情熱」を表す色。ふだん色気のない私でも、ここぞというときには赤を着たくなるときがある。赤は華やかだし、着ることで気持ちが前向きになる「勇気をくれる色」だと思っている。
では自然の中で赤はどんな色だろうか。
身近なところではわたしたちの体内を流れる血の色であり、生まれたての赤ちゃんの色。植物でいえば常緑樹の新芽は赤色をしているし、冬が到来する前に山が一気にみせる紅葉の色でもある。赤は自然界において季節の変わり目にポッと現れるメッセージのような色なのだ。そして子どもを生み育てる女性にも毎月その印は現れる。
赤を生命に関する神秘を秘めた色であり、パワーを秘めた色として祭祀などで多用されたのではないだろうか。
大船遺跡に暮らした人々が、竪穴住居の床面に赤土を選んだかどうかは「わからない」が、土をどう見分けるかという視点がなければ、地面に穴を掘る竪穴住居の暮らしは成り立たないように思う。もし縄文人に脈々と語り継がれた土選びの知恵があったなら、「赤土を選べ」という教えがあってもおかしくないのではないか。

生きのびるためのまじない
福田さんからは、大船遺跡にある別の竪穴住居の床面から胎盤(胞衣)とみられる成分が検出されたことも聞いた。胎児と母体をつなぐ胎盤を小さな壺に入れて人に踏まれるところに埋める胞衣納めは、たくさんの人が踏むことで丈夫に育つとして、自宅出産が行われていた昭和の始め頃まで続いていたまじないだ。
そもそも子どもは身体が未熟で感染症にかかりやすく、いつ死んでしまうかわからない。国の人口動態統計をみると、新生児が1年以内に亡くなる割合は昭和の初め頃までで10人に1人。医療が発達する以前の出産は命がけの行為であり、命を落とすのは母親であることも少なくなかっただろう。
昔の人は病気や災いを魔物のしわざとしたから、魔除けのまじないがさまざまに発達したのだ。大船遺跡の人々も生きのびるためにさまざまなまじないを行っていたに違いない。

縄文時代の古人骨の研究によると、北海道や東北のような寒冷地ほど多産多死の傾向が強くなるそうだ。先ほどの縄文交流センターでは、粘土に子どもの足形を押しつけて、ひもを通して吊るせるようにした土版をみた。センターの南側斜面に広がる垣ノ島遺跡から出土したものだ。子どもの成長を祝った記念なのか、それとも亡くなった子どもの形見なのかわからないが、これもまた、まじないを感じるものだった。
目の前に広がる海は、大漁と不漁、シケと凪、ラッキーとアンラッキーが隣り合わせで、食料をくれるが簡単に人の命を奪う大きな力を持っている。人間は自然界におけるちっぽけな存在なのだ。
だが、大船遺跡の人々はやられてばかりではなかったと思う。なぜなら、人々は津軽海峡を渡ったし、条件のよい土をめざして掘ることもできたのだから。大船遺跡の人々は潮流や地質を見分ける目を持っていた。それは、人々が自然を五感で観察し、そこに法則性を見出していたからではないだろうか。
私は、はるか昔にここで暮らした人々が自然と対話していたことを想像する。胞衣を土に埋めるように、みえない力に働きかけようと、さまざまな方法で「ツキを呼び込む」努力をしたように思う。
リアルな世界と目にはみえない世界。その両方から考えないと、縄文文化の本質はみえてこないのだと思う。赤い色にこだわるのも深すぎる竪穴も、人々が自然界の神々から「いかに愛を引き出すか」を真剣に考えた痕跡かもしれないのだから。

遺跡に行こう!
先に博物館で出土したものを見てから遺跡に行くと、イメージがわきやすい。博物館は休館日を確認するのを忘れずに。
函館市縄文文化交流センターの海側にある垣ノ島遺跡は2021年に向けて整備中だ。
【大船遺跡】
北海道函館市大船町575−1
https://jomon-japan.jp/jomon-sites/ofune/
【函館市縄文文化交流センター】
函館市臼尻町551-1
電話番号:0138-25-2030
http://www.hjcc.jp/