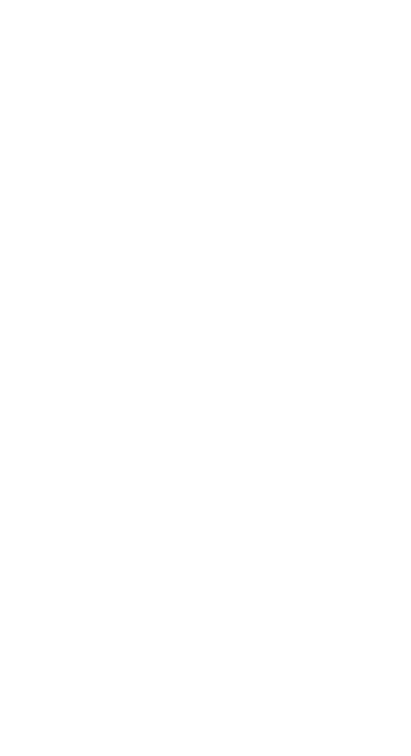JOMON TRAVEL縄文を旅する
縄文アート/中国なぜ若き縄文アーティストはリアルをめざしたのか〜村上原野くんを偲んで Part.2
勾玉でできたアート
陽も暮れて薄暗くなってきた。野炉の周りが落ち着いていたので、校舎に展示された原野くんの作品を見ることにした。猪風来さんに案内されて1階の展示室に入ると、そこは法曽焼作品の部屋だった。法曽焼とは、美術館のある法曽地区で江戸後期に途絶えてしまった幻の陶磁器で、それを現代に復興をしたのも猪風来さんの功績のひとつだ。展示室には、猪風来さんの法曽焼作品のほか、原野くんの手がけたものもあった。
それは8月30日まで開催中の企画展「地より来て地に還るもの」のメインとなる作品だった。猪風来さんの話しによると、絶作の前作にあたるもので「死」をテーマにしているという。赤黒い陶磁器上に鈍く光って流れる渦の起点を指さした猪風来さんは「これはすべて勾玉でできているんだ」と話す。よく見ると、目の前の作品は、勾玉のしっぽを伸ばしたスパイラル文様で埋めつくされていた。
勾玉は縄文時代から古墳時代まで装身具として作られてきたものだ。勾玉の形については、動物の牙を原形とする説や、半割れした玦状耳飾りを再利用したものなどいくつかの説があるが、猪風来さんは「胎芽(胎児の前の段階)の形で、すべての生命の源を表している」として、呪術具だと捉えている。
母親の子宮に着床した小さな受精卵は分裂を繰り返し、魚から両生類、は虫類と、生物の進化の形を辿るが、その初期の形はどの生物も同じ勾玉のような形をしている。猪風来さんは狩猟をしていた頃の人々は、そのことを知っていたと踏んでいる。なぜなら、仕留めた動物を解体し、食べるのが当たり前の暮らしだったからだ(さらに付け加えるなら、流産の多い時代で、自分から流れてしまった胎芽を見る機会があったということも留意しておきたい)。胎芽をいのちの最初の形として認識していた古の人々は、そこに見えない力を感じ、見たままに勾玉をつくり、さらにその形を発展させて土器の上に渦を描いたとする考えが、猪風来さんの縄文芸術の根幹をなしている。
その思想は原野くんにも受け継がれ、より明確にキレのあるスパイラル造形となって、目の前に置かれていた。下から沸き立つようにのぼるいくつもの渦の真ん中にはどれも勾玉があった。じーっと見ていると吸い込まれそうになるサイケデリックな渦は、S字を描きながら上昇し、トップで角を持つ雄鹿の頭に変化していた。その目は勾玉の生命感を断絶するように閉じられていた。リアリズムへの道は、この頃から始まったのだろうか。絶作へ至る道が少しずつ見えてきた。
猪風来さんは野焼きの現場に戻り、私たちはさらに原野くんの作品を見るために2階の展示室へと上がった。階段を登って左の奥にある部屋に入ると、釉薬のかかっていない野で焼かれたザラザラとした土器がずらりと並んでいた。
原野くんは父の猪風来さんに弟子入りしたとき、3年間徹底的に縄文土器の模写を叩き込まれた。猪風来さんが縄文のスピリットを体得するために北海道の原野に分け入ったように、縄文1万年の手仕事を自分のものにするには、まず模倣からというわけだ。壁際には、その頃作ったと思われる縄文土器や土偶が並んでいた。すべていちから粘土を輪積みして作ったものだと思うが、型取りしたレプリカに見えるくらい本物そっくりだった。
次に原野くんが初期に作ったオリジナル土器を見る。それが初期の作品だと知っているのは、この土器を焼いた2014年の春の野焼きに私たちも参加していたからだ。口縁部が流線型になった土器は、jomonism代表で3DCGデザイナーの小林武人がライブペインターの坂巻義徳 a.k.a sense の絵をモデリングし、3Dプリンターで出力したパーツを原野くんに渡して出来たコラボ土器だった。
最初にこの作品をみたとき、土でできた土器なのに、モーターショーに展示されるコンセプトカーのような近未来感を感じたのを覚えている。それは口縁部についた武人のパーツから受ける印象だけではなかった。改めてじっくり観てみると、文様を構成する線に迷いがなく、とてもシャープなのだ。曲線にキレがあるので、スピード感が出る。何のスピードかというと、竹べらを持つ手のスピードだろう。そのスピーディーで流れるような文様が、流線型を描くコンセプトカーのようにキレキレに見えるのだった。
当時、出来上がった作品を見た武人はこんなことを言っていた。
「ずっと模写をしていたからだと思うけど、人のラインをたどるのがすごくうまい。パーツから流れるラインの部分とか、何も言わなくても僕らの形を理解してくれている。すごいと思った。仕上げもとても丁寧だし、土っぽくて自然な雰囲気の猪風来さんの作品とはまた違うんだよね。縄文と現代の感覚が原野くんの中で融合して次世代の土器に昇華されているんだよ」
2年程前になるが、ある縄文ムック本の記事を書くにあたり、原野くんに簡単な電話取材をしたことがある。そのとき彼は初期の創作の源流を北海道で過ごした幼少時代の原風景に求め、あの頃の自分にあった縄文(子ども)の感性を掘り起こすことから始めたと言っていた。そしてこう話していた。
「縄文土器の文様には世代を越えて語り継がれ、地層のように蓄積された世界観があるのだから、その世界観を、現代の自分も学び、取り込んで、次の人間に新たな縄文の種として引き継いでいきたい」
その言葉通り、初期の頃と思われる作品には二つのリングが表裏一体になった双眼や三つ又の三叉文、縄目といった縄文土器に見られる形が散りばめられていた。しかし、順を追うごとに縄文土器っぽさはなりを潜め、曲線への過剰な追求が行われていくのがわかった。部屋の中央に並んだ作品群になると、文様が意志を持った生命体のように大きくうねり、アメーバ状にねじれている。口縁部は閉じられ、もはや器でもなかった。
縄文土器の中には、中部高地に見られる水煙文土器や信濃川沿いの火焔型土器、あるいは3D感が半端ない会津式土器のように過剰な装飾性、立体文様を持つ土器があるが、あれらはあくまでも鍋や瓶といった生活用具だった。縄文土器の面白さはそこにある。なぜ煮炊きに使う鍋に複雑な文様を施したのかということについては、山岡さんの監督した『縄文にハマる人々』を参考にして頂きたいが、縄文土器のデザインは土器の中身(食料としての植物や動物)との関係や、狩猟採集民の世界観(神話観)の共有、血族や出身を表す必要性など、様々な理由があった上で機能していたものだと思う。
しかし、猪風来さんも原野くんもそのような背景から一切切り離された現代に生きている。現代における土器の創造は自己表現なのであって、とくに鍋や器である必要性はない。だから、原野くんは縄文土器の大前提である「器」から離れ、文様のエッセンスを抽出したエネルギー体のようなオブジェとして表したのだろう。
2年前の電話取材で原野くんが話していた内容を紹介したい。
「いま作っている作品は、渦を巻いて動き続けるという縄文(文様)本来の特徴をよりダイナミックに表現したもの。縄文の伝統的な様式には法則性があるが、様式の移り変わりの中でうつろうもの。一万年以上、縄文たらしめた根源にある精神性や哲学が大事で、僕は、自分の作品に”いのち”を込めている。それは土器そのものが”いのち”であるという哲学なんです」
文様(パターン)というものは、制限がなければどこまでも無限に増殖することができる。イスラム教寺院などの例をみても、壁・天井・床などの平面は、アラベスク文様で敷き詰められているはずだ。こと粘土での文様表現になると、平面という制約もなく、文様は縦横無尽に動ける。そのありさまは、自然界のいたるところで増殖するものたち(枝を広げる樹木や樹皮に根を卸す地衣類、生い茂る野草、春になると湧きだすカエルの卵など)の姿に見ることができる。そのような途切れることのないいのちのループは、ときに美しく、ときに恐ろしくなるほどグロテスクだ。そして、生命の持つそのような本質が原野くんの作品群にはよく表れているのだった。
「グロテスク」「装飾」という言葉についての補足
現代では漠然と「気味の悪いもの」をさす「グロテスク」だが、ケルト美術研究の第一人者である鶴岡真弓さんの『「装飾」の美術文明史』(NHK出版)によると、グロテスクという言葉は15世紀の皇帝ネロの「黄金の館(ドゥムス・アウレア)」の洞窟(グロッタ)を連想させる半地下の壁に描かれていた奇妙で不合理で過剰な装飾に起因するという。廃墟となったその建物を再発見したのは、16世紀のイタリア・ルネサンスのラファエロをはじめとする芸術家たちで、植物から人間へ、鳥が人間へ、などという空想に満ちた装飾に刺激を受け、こぞって装飾表現に取り入れたことから、「グロッタ」もの、すなわち「グロテスク」と呼ばれるようになった。鶴岡さんは、ルネサンスの芸術家たちが膨らませたグロテスク装飾は、「ありえない自然」であり「反自然」的だが、同時に細部に徹底した自然観察による自然主義が見られると指摘している。
つまり、「グロテスク」という概念は、もともとは古典美の復興と徹底した自然観察によって創作された装飾の世界から生まれた言葉であり、人を惹き付ける魅力に満ちた世界観があることをここに書いておきたい。ついでに「グロテスク」の語源となった「洞窟」についても言及すると、人が住居で暮らす以前の住まいは洞窟だった。長い期間、暗闇とともに暮らしていた人間には闇という属性があり、それが古い段階の文化では、ストレートに表現されていることが多い。そこにルネサンスの芸術家たちも反応したのではないだろうか。美という価値観は人によってさまざまだが「美しさ」を求める人間の心性は、闇(グロッタ、グロテスク)を知っているから生まれたこと。闇がなければ、美もないのである。
また、縄文土器の文様は「装飾」ではないと思われる方もいるかもしれない。「カザリ」という言葉に対して嫌悪感を抱く人は多いのか、この本もまた、「いつの世にも人は虚飾に欺かれる」というシェイクスピアの『ヴェニスの商人』の引用から始まり、「人は『飾り』とか『装飾』というものを、反射的に『嘘』や『愚かしさ』と結びつけてみることが多い」と指摘している。そして、その考え方が最高点に達したのが、20世紀のモダンデザインにおける、建築家ミース・ファン・デル・ローエが提唱した「レス・イズ・モア(飾りを少なくすればするほど、より機能的な生活ができる)」なのだと。
しかし、飾ることは人間だけが行う行為ではない。「蝶の羽や魚の皮膚や草木の蔓草や花びらなど、自然界全体が『装飾』の営みを持っている。そのなかで人間も『飾る動物』の一員」であり「単に人間の芸術行為に『カザリ』が添えられるというのではなく、文化のコアから現れる人間存在の本質の部分、それが『装飾』」なのだと。その文脈で言えば、縄文土器の文様とは芸術が生まれる以前にあった、この「装飾」行為の源流にあたるものだと思う。そこには、洞窟のごとく真っ暗な竪穴住居で暮らしていた「闇を知っている」人々が求めた、美の形があるはずなのだ。
( Part3へ続く)
村上原野くんの作品が見られる展覧会
「村上原野追悼~渦巻く翅(つばさ)のヴィーナス展」
会期 2020年9月1日(火)~12月26日(土)
休館日 月曜日(冬期12月~1月は月・火曜日)
猪風来美術館(新見市法曽陶芸館)
岡山県新見市法曽609 TEL・FAX (0867)75-2444
詳しくはコチラ
「縄文のスピリットに基づきながら現代に生きる己の感性で
土と炎と大自然に向き合い、縄文の新時代の美を求めてゆく。
やがて皆がそれを感じ、縄文のあたらしい渦が新星のように
生まれてゆく時代――スパイラル・ノヴァの訪れを予感しています。」(村上原野)
今年2月16日未明、作品制作中に手に竹べらを持ったまま32歳の若さで突然逝ってしまった村上原野。
完成直前の絶作となった「渦巻く翅のヴィーナス」をはじめ、10年間に渡って制作された渾身の珠玉作品と
その濃密な創作の過程を一挙展示します。