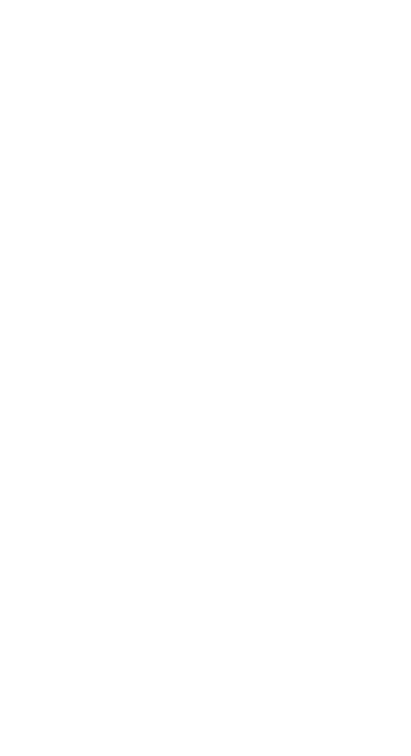JOMON TRAVEL縄文を旅する
縄文アート/中国なぜ若き縄文アーティストはリアルをめざしたのか〜村上原野くんを偲んで Part.3
火と向き合うということ
校庭に戻ると、山岡さんが「ものすごく艶かしくなっていますよ」と野炉の作品を指して言った。最初に据え置かれたときよりも、表面がねっとりと艶を帯び始めていて、まるで汗をかいているように見える。心なしか色も黒ずんだ気がする。炎によって粘土の中で化学変化が起こり始めているのだ。
野焼きに立ち会うと、火の力を思い知らされる。いまこのあぶり焼きの火ですら、1mも近づけないほどの熱量がある。これが明日の本焼きになれば、太陽からの熱量も加わり圧倒的なパワーとなって土器を覆い尽くすのだ。土器は火の力の賜物。腐ってなくなることが宿命の有機物だらけの世界にあって、土を半永久的な形にしたのが火の力だ。火の利用は科学の始まり。鉱物から銅や鉄などを精錬するのも火を扱える技術がなければ始まらない。人間は火を扱うことを通して文明を切り開いてきた。
しかし、いつしか私たちの社会は火を避けるようになった。囲炉裏の火はストーブに代わり、ゴミの野外焼却はダイオキシンが発生するとして禁止された。やがてストーブもエアコンに置き換わり、IHコンロを導入したオール電化の住宅にする人も少なくない。今ではキャンプ場やBBQ場といった限られた場所でしか火を焚くことは許されていない。この野焼きも、消防や自治体への届け出を出した上で行われているはずだ。
たしかに火は危険だし、環境問題にも配慮しなければならない。しかし、暮らしから火を使う機会がなくなることの方が、いろんな意味でリスクがあるような気がしてならない。なぜなら、火の危険性を学ぶ機会ごとなくなるわけだから。
その意味で、土器を焼く野焼きは火の扱い方を学ぶよい機会だと思う。小さな火から大きな火まで体験でき、化学繊維の服は溶けやすいとか、風の強さで火がどう燃えるか、乾燥した木材の火付きの早さなども体感でわかる。猪風来さんはより多くの人が縄文の精神を理解し、縄文造形が定着することを願って、年に2回、春と秋に野焼きを行っているが、それは裏返すと、火の教育をしているようなものだ。土器がうまく焼けるということは、火を上手に扱えるようになった証でもあるのだから。
野炉の周りでは、女性たちが燃えている柱に臆することもなく手をかけて、炎の位置を整えていた。火の扱いがうまく阿吽の呼吸でことが進んでいくのは、見ていてとても安心感があった。
訪れたスランプ
今回の野焼きに集まった人たちは、年齢の幅もさまざまだ。近隣の方もいれば、あきちゃんのように岡山に移住してきた人、旅の途中で偶然ここを見つけ、以来野焼きに参加しているという遠方の方もいた。みんな原野くんの追悼がしたいと集まった方々だった。
広場の端にある工房では、それら参加者が自由に食べられるよう、おにぎりや豚汁、サンドイッチのほか、持ち寄りのお菓子や惣菜が大量に用意されていた。そのテーブルの上に、今年の春の野焼きで焼いたという原野くんの遺作が2つ並んでいた。
小ぶりな作品のほうは、ゆるいカーブを描くS字文様が上へ上へと延びており、透かしの入った面白い形をしていた。しかしもうひとつの作品は、下から続く華麗な文様帯が口縁部で唐突に途切れ、のっぺりとした無文部で終わっていた。
猪風来さんによると、原野くんは口縁部まできて、突然この続きが作れなくなったという。超絶技巧の持ち主で、追求するテーマもしっかり確立していた原野くんが、これを境に冬まで粘土を握れない日々が続いたというのだ。いったい何があったのだろう?
それは、一昨年(2018年)の夏のことだという。ちょうど東京の国立博物館で「縄文―1万年の美の鼓動」展が開催され、縄文ブームが沸き起こっていた頃だ。山岡さんの『縄文にハマる人々』も公開され、映画に登場した猪風来さんや原野くんにも注目が集まっていた時期だと思う。理由はわからないが、子どもの頃から疑いもなく触ってきた粘土への思いがしぼんでしまったのだ。それは粘土を触る自分への信頼が失われてしまったということではないだろうか。
母親のよしこさんにそのときの原野くんの様子を聞くと、粘土造形ができなくなっただけでなく、対人での関わりを避けて、なかば“うつ状態”のようだったという。本人から「そっとしておいてほしい」という要望があり、猪風来さんもよしこさんもストレスを与えないよう見守るしかなかった。しかし、あるとき急に『山に行きたい』と言い出した原野くんは、テントや寝袋をもって、ひとりで隣接する広島県の山に出かけたという。
ある意味、それはネイティブアメリカンにおける成人の通過儀礼、ヴィジョンクエストのような体験だったのだろうか。将来的に猪風来美術館を継いでいくことが決まっていても作家として確立できるかはまた別の話しであり、自分は何がしたいのか、どうあるべきなのかなどと色々考えたいことがあったのだろう。原野くんは山から還ってくると、翌春に決まっていたアメリカでのワークショップの準備に少しづつ取りかかるようになったという。
アメリカ行きの話しは、jomonismのメンバーである陶芸家の大藪龍二郎がその前年度にアメリカに住む友人と企画した続編にあたる機会だった。このとき原野くんはアメリカ側との対応を行い、猪風来さんとともにコロラドの大地で陶器をつくり、野焼きを完遂した。それら一連の経験が糧になったのか、帰国後は吹っ切れたように再び粘土に向き合えるようになったという。そこで生まれたのが法曽焼の雄鹿の作品だ。原野くんは半文半獣の表現に手応えを得たのだろうか。次に半文半人の縄文のニケ(仮題)に挑むのだ。
外に出ると、新月だというのにそれほど星が見えなかった。薄く曇っているのかもしれない。そのせいかそれほど冷込みもきていなかった。野炉では燃焼時間の長い太い木材が時折火の粉をあげて、おだやかに燃えている。野炉の脇で、あきちゃんが静かに涙を流しながら物思いにふけっていた。他の人たちも静かに野炉の作品を見守っていた。深夜0時を過ぎ、女性から男性へ野焼きスタッフの交代が行われたところで私たちは引き上げ、美術館内の使っていない展示室で寝袋を敷いて寝た。
炎を吸って色を変えていく
翌朝、5時を過ぎたところで猪風来さんが私たちを起こしに来た。本焼きが始まるという。火を強めるのは6時か7時くらいからと聞いていたのにだいぶ早い。きっと野炉の土器が待ってくれないのだろう。校庭に出て、寝ぼけ眼で野炉を見ると、青みがかった朝の薄明かりの中で原野くんの縄文のニケ(仮題)はびっくりするぐらい真っ黒になっていた。これは粘土の温度が上がり、煤の吸着が進んだためだ。猪風来さんが丹念に磨いた表面はブロンズ像かと思うくらい黒光りしていた。
火円陣の範囲はだいぶ狭まり、男たちが太い材を井げた状に組んでいく。こうして炎の高さを出していくことで、作品は火で包まれる。その状態を猪風来さんは「火の子宮」と呼ぶ。土は650℃を越えると粘土に戻らなくなるという。土の中に含まれる結晶状の水分が650℃を境に飛ぶためだ。それ過ぎると、粘土の色は黒から赤へと変化するそうだ。猪風来さんの野焼きでは上まですっぽり炎で覆う子宮状態で800℃や900℃を目指す。
7時を過ぎると山際から朝日が差し込んできた。轟々と火力を増した野炉から天に向かってつむじ風が巻き起こり、そこに朝日が当たって何かの合図のように見えた。作品の下半分が赤く染まり出したのが肉眼でも確認できる。問題は、複雑な造形をした背中側で、そこも均等に温度を上げていくために猪風来さんは後ろ側の火の当たり方により注意を払っていた。
8時半を過ぎ、野炉の周りで歓声があがる。とうとう炎の高さが作品を越え、井げたの上に板材が渡されたのだ。作品は炎に包まれとうとう見えなくなった。野焼きの最終局面である火の子宮だ。仕上げに細い枝が周囲に立てかけられると、炎が天を目指して立ちのぼる。一同静かに見守ると、燃焼して弱まる炎の中から、全体が赤茶色に染まった作品が表れた。煙の中から表れた姿は、まさに「ヴィーナスの誕生」といった初々しい雰囲気で、難産で生まれた子どもみたいだった。それまでの緊張感がほどけ、抱き合って涙する参加者もいる。きっと、この瞬間を一番見たかったのは原野くんだっただろう。
2014年に原野くんが最初にオリジナル土器を焼いたとき、感想を聞いたら「わが子のようです」と笑って答えたのを思い出す。その笑顔の後ろに束ねられた髪の毛先はちりちりに焼けていたっけ。雄鹿の作品が「死」をテーマにしていたことから、この作品のテーマは「生」なのではないかと猪風来さんはいう。その「生」の実感は、野焼きという火との丁々発止のやりとりを経験して得られる深い実感なのかもしれない。原野くんは、熱と格闘してものを生み出すことの清々しさを感じていたんだな。
土の手触りや火の熱量が魅了する世界がある。そこは、人間界と自然界がちょうど重なり合う地点。自然界の生き物はDNAというプログラミングされたコードによって、いのちをつなぐように設計されているが、原野くんはきっとそのコードを粘土で表現しようと奮闘していたに違いない。この粘土でどこまで複雑にできるか。重力に逆らってどこまでのばすことができるのか。あらゆるパワーバランスの整合性をとりながら、常に変化し続けるいのちの躍動感を焼き付けようとした。シンプルなモダンデザインに慣れた私たちは、そのうごめく姿にぎょっとする。けれど、文様に埋め尽くされた作品は、こう訴えかけてくる。人間もまた変化し続ける自然の一部なのだということを。
—
なぜ原野くんはリアリズムをめざしたのか。そのことに大きく関係する話としては、やはり女性との出会いがあったということを最後に書いておきたい。その女性の心境を察すると、詳しくはここに書かないが、原野くんは幸せの絶頂にいた。最愛の人との出会いが土器の女神化を後押しした原動力となったのは間違いないようだ。
(FIN)
村上原野くんの作品が見られる展覧会
「村上原野追悼~渦巻く翅(つばさ)のヴィーナス展」
会期 2020年9月1日(火)~12月26日(土)
休館日 月曜日(冬期12月~1月は月・火曜日)
猪風来美術館(新見市法曽陶芸館)
岡山県新見市法曽609 TEL・FAX (0867)75-2444
詳しくはコチラ
「縄文のスピリットに基づきながら現代に生きる己の感性で
土と炎と大自然に向き合い、縄文の新時代の美を求めてゆく。
やがて皆がそれを感じ、縄文のあたらしい渦が新星のように
生まれてゆく時代――スパイラル・ノヴァの訪れを予感しています。」(村上原野)
今年2月16日未明、作品制作中に手に竹べらを持ったまま32歳の若さで突然逝ってしまった村上原野。
完成直前の絶作となった「渦巻く翅のヴィーナス」をはじめ、10年間に渡って制作された渾身の珠玉作品と
その濃密な創作の過程を一挙展示します。